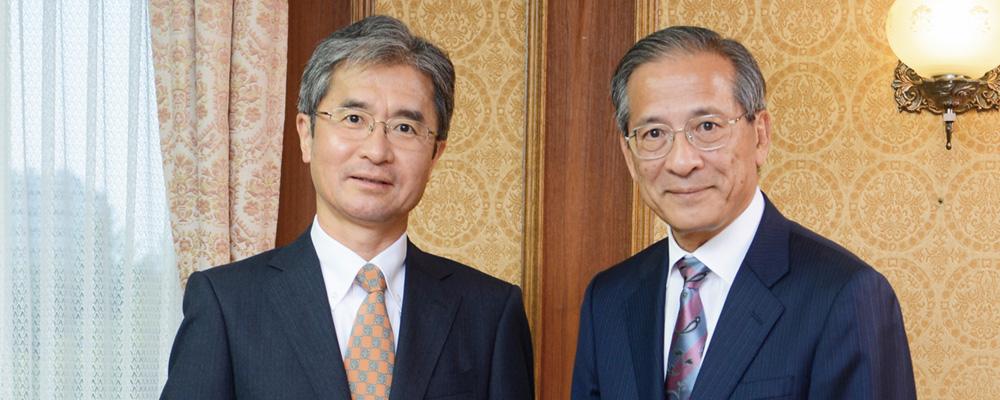"経営者人材"の育成とは
- 株式会社ミスミグループ本社取締役会議長
一橋大学大学院商学研究科客員教授三枝 匡 - 一橋大学長蓼沼 宏一
2015年秋号vol.48 掲載
世界的なコンサルティング・ファームのコンサルタントや、業績不振に陥った日本企業の再生専門家の仕事を経て、株式会社ミスミ(現・ミスミグループ本社)の社外取締役に請われ、翌年には社長CEOとなり、同社をグローバル企業集団に発展させた三枝匡氏。"経営人材の育成"を経営テーマに掲げて、ミスミだけでなく、日本の次世代経営者を育成することに心血を注いできた功績は大きい。母校である一橋大学でも、客員教授などの立場で過去9年にわたり教鞭を執ったほか、「三枝匡経営者育成基金」を設立、多大な貢献をしている。そんな三枝氏に、自身の人生とともに経営者人材育成の要点を伺った。

三枝 匡
1967年一橋大学経済学部卒業。三井石油化学を経て、20代でボストン・コンサルティング・グループの国内採用第1号コンサルタントになり、その後スタンフォード大学でMBAを取得。プロ経営者になりたいとの志を抱き、30代では赤字会社2社の再生とベンチャーキャピタル会社の経営者を経て、41歳の時に株式会社三枝匡事務所を開設。不振企業を再生するターンアラウンド・スペシャリスト(事業再生専門家)として16年間活動。2002年、東証1部上場企業ミスミグループ本社の社長CEOに就任。同社を12年間で従業員340人の商社からグローバル9000人の国際企業に変身させた。2014年にCEOを退任、現職。一橋大学大学院商学研究科(MBAコース)客員教授を兼務。著書に『戦略プロフェッショナル』(ダイヤモンド社刊)、『経営パワーの危機』(日本経済新聞社刊)、『V字回復の経営』(日本経済新聞社刊)など。

蓼沼 宏一
1982年一橋大学経済学部卒業。1989年ロチェスター大学大学院経済学研究科修了、Ph.D.(博士)を取得。1990年一橋大学経済学部講師に就任。1992年同経済学部助教授、2000年同経済学研究科教授、2011年経済学研究科長(2013年まで)を経て、2014年12月一橋大学長に就任。専門分野は社会的選択理論、厚生経済学、ゲーム理論。近著に『幸せのための経済学──効率と衡平の考え方』(2011年岩波書店刊)がある。
経営における「戦略」という仕事に痺れるほどの面白さを感じた
蓼沼:三枝さんは、一橋大学を卒業後、ボストン・コンサルティング・グループ(以下、BCG)に国内第一号のコンサルタントとして加わり、スタンフォード大学のMBAプログラムを経て、30代で日本企業三社の経営トップ、その後独立して、"ターンアラウンド・スペシャリスト(事業再生専門家)"として多くの企業再生に携わられました。当時の同級生たちとはかなり異質な経験を積まれたと思います。まずは、そのあたりのことからお聞かせください。
三枝:大学を卒業した後は、多くの一橋大学出身者同様に日本の大企業に就職しました。しかし、2年半ほどで物足りなくなったのです。自分の人生観とはちょっと違うぞ、と。しかし、当時の日本は、転職は社会の順当な道から外れることだと思われていた時代でした。一橋大学の恩師である板垣與よ一いち先生に相談したところ、「これからは国際化の時代だよ」と仰り、BCG日本支社の初代社長を務めていたジェームズ・アベグレン博士を紹介してくださったのです。アベグレン氏は、"終身雇用""年功序列""企業内労働組合"を「日本的経営の"三種の神器"」と分析し、『日本の経営』を著して、世界に日本経営を紹介した先駆者でした。
BCGは今でこそ全世界に5千人を超えるコンサルタントを擁する世界屈指のコンサルティング会社に発展していますが、当時はボストン本社でも30人ぐらいしかいない、小さな事務所でした。しかし、創業者のブルース・ヘンダーソン氏は、それまで軍事用語だった"戦略"という概念を世界で初めて具体的な経営フレームワークに高め、欧米の名だたる企業がそれを学んで経営に組み込むことになり、70年代を「経営戦略の時代」と言わしめるようなブームを引き起こした人物でした。彼の周りには、望めばハーバード大学の教授を務められるような逸材が集まっていました。私は転職について大いに悩みましたが、半年後に決断しました。結果的に、私が自分の人生で下した最良の決断の一つになりました。25歳で転職してみると、ヘンダーソン氏の戦略フレームワークは実に明快で、私はその魅力に痺れるほどの面白さを感じました。その後、アベグレン氏の配慮で私はボストンの本社に移り、そこを起点にして欧米企業に対するコンサルティングに従事しました。アベグレン氏がミラノで日本的経営についてのセミナーを開催した際は、私もプレゼンテーションを行いました。まだ20代後半でしたが、これらの経験が私にとって企業経営に対する大きな知識的ベースになりましたね。
自ら経営者としての力がついてきたと思えた瞬間

蓼沼:最初の転職は誰でも悩むものですが、そのうえでの決断だったのですね。そんな三枝さんが20代の最後の頃から、コンサルタントではなく、やがて経営者になりたいと考えるようになったと伺いました。経営者として人や組織の上に立って采配を振るう立場を目指すというのは、かなり大きな発想の転換があったと思うのですが、それを意識するようになったのはどのような理由からだったのでしょうか?
三枝:コンサルタントをあまり長くやると、かえって経営者への道から遠ざかると考えるようになったのです。コンサルタントの仕事とは、有り体にいうと、まずは経営者がギクッとするような問題を指摘して、危機意識を喚起し、コンサルティング業務を受注することがポイントになるわけです。コンサルタントの仕事は、外部からの視点をもって行われる短期的プロジェクトの繰り返しです。会社の外からだと、危機意識を持たせ、経営の流れを変えさせるために過激なこともどんどん言えますが、社内に入って会社の経営責任を担う立場になれば、目先の過激さで社員を刺激するよりも、長期的視点から事業や組織をどう構築していくかという長丁場の勝負も非常に重要になってきます。また、現場に立脚する経営者は、現場のドロドロしたことにも対処しなければなりません。理屈もさることながら、人々の感情や意欲にどう応えていくかという問題が大きいわけです。そこで、私はコンサルタントの仕事はある程度で切り上げて、経営者の道を歩みたいと考えました。スタンフォード大学でMBAを取得した後、シカゴに本社のあるアメリカの企業に転職してアメリカ人社長のアシスタントに就きました。ここでは米国や欧州での社長特命プロジェクトに関わりました。
蓼沼:なるほど。三枝さんはまず、米国経営者の間近で働く環境に入られた。そこから、ご自身の経営者としての勝負が始まったわけですね。
三枝:はい。その時の経験で私は米国の経営スタイルに染まったわけではなく、米国企業トップの切れ味の良さには感心しましたが、反面、米国企業組織の欠点や弱さも冷静に見ていたと思います。その米国企業がある日本の財閥系企業と合弁会社をやっていて、私は1年後に帰国し、米国側から送り込まれる形でその会社の常務取締役になりました。まだ32歳でしたが、私は初めて部下を持ち、日本の競争相手と激烈な戦いをしていた事業の上に立ちました。その1年後には会社のトップに就任し、初めてトップ経営者の立場に立ったわけです。その後、2社の社長を経験し、変化の激しい30代を過ごしました。41歳になって、株式会社三枝匡事務所を設立しました。独立してしばらくすると、経営不振に陥った日本企業の事業再生を引き受けるようになりました。外部者としてではなく、相手企業の副社長や取締役などの立場で内部に深く入り込み、2年から4年くらいの期間をかけて、その会社の事業再生に当たるというスタイルでした。自らは「現場で指揮を執る経営者」という意識でした。
蓼沼:普通の日本人ではなかなか経験できない30代を過ごされたと言ってよいでしょうね。ところで三枝さんは、経営者人材の育成を人生の重要なテーマにしておられます。そのお考えをもつようになったのはいつ頃のことでしたか?
三枝:会社を立て直す仕事では、死の谷とも呼べるような困難な状況に何度も出会い、いろいろな経営経験を積みました。50代に入った頃には、人からプロ経営者と呼ばれることがあっても、おこがましいのですが、それに近い力がついたのかなと思える瞬間が何度か重なりました。そうなってくると私は自分の経営技量よりも、むしろ次世代の経営者人材を育てることが私の人生の役割だと思うようになりました。
蓼沼:三枝さんが一橋大学の教壇に立たれるようになったのも、そのような意識があったからですね。そこまで三枝さんが使命感を抱くようになった背後には、かなり強烈な出来事をいろいろ経験されたのではないでしょうか。
三枝:業績で追い詰められた企業には、受け身で、改革意欲のない社員がたくさんいるわけです。そういう人たちの多くは性格的にはとてもいい人たちなのですが、改革となれば背を向けたり、行動をサボる人が多い。そんな組織をどう変えて社員の目が輝くようになるかが、改革では問われるわけです。押したり引いたりの繰り返しで、中には自分のほうが追い出されて悔しい思いをしたケースもあります。そんな経験を積み重ねる中で、私は自分の経営者としての力量を徐々につけていったと思います。病気になった企業を再生するということは、その企業をダメにしてしまった歴代経営者よりも自分のほうが経営力で上でなければ、お役には立てません。そうした活動の中で、日本企業が元気を失った最大の理由として、社内で経営者人材の育成が遅れている問題を痛感する場面が繰り返されたのです。ダメになる企業は、とどのつまり経営リーダーの力量が足りないことが最大の原因であるということが見えたわけです。商品開発や市場の変化など、事業がダメになる要因はたくさんあるわけですが、カギは「人の問題」だと。バブルが崩壊して一斉に企業業績が悪化しても、それを打開する人材がなかなか出てこなかった。過去の繁栄から一転して90年代の不振に落ちていく中で、経営の苦境に立ち向かえるような鍛えられ方をしている社員が圧倒的に少ないことが判明したのです。私がそんな問題意識を基にして1994年に出版したのが、『経営パワーの危機』(日本経済新聞社刊)という本です。日本企業の苦境は経営者人材の枯渇が原因であり、そうした「組織劣化」は、実は80年代にすでに始まっていたことを指摘する本でした。
蓼沼:たしかにバブル崩壊当時、景気が悪いのはマクロ経済政策の問題だという意見が声高に語られていたように思われます。しかし今では、日本企業の間で、経営不振の根っこには人材問題があるという認識はかなり高まっていますね。
フレームワークと学問や科学の共通性
蓼沼:お話を伺って、経営のプロとなるためには、理論と経験の相互作用が必要だと感じました。BCGやスタンフォード大学で理論やフレームワークを学ばれましたが、それだけではなく、経営困難な会社の現場、いわば"修羅場"に何度も身を投じて経験を積まれたことが、三枝さんの人間としての基幹をつくっているように思います。

三枝:強い企業は、必ず明快な「経営フレームワーク」をもっています。企業経営のベースには、必ずその企業なりのしっかりした論理があると思います。
もちろんその論理は競争上優れているものでなければなりませんが、どれだけ優れた論理やフレームワークであっても、それを社内の組織にどのように落とし込み、それをどう使って事業を動かしていくのかという、「トップ戦略から現場組織への、つなぎの部分」が問われるわけです。
高い費用を払って経営コンサルタントに依頼しても、それを現場経営にまで落とし込むことができなければ、費用をドブに捨ててしまうのと同じになってしまいます。私は、20代で経営コンサルタントとして戦略のフレームワークを修得しましたが、30代以降は戦略をトップ経営者レベルだけのものにしないで、企業の組織末端の若手社員の考え方や活動にまで、どう落とし込んで組織的エネルギーを束にするかということの試行錯誤を繰り返しました。私がラッキーだったのは、出発点がBCGだったことです。世界的な企業経営者が語る実践的な戦略理論やフレームワークに人生の早い時期に触れ、次にそれを自分自身の経営経験の中で実行に落とし込むことをしてきた。教科書に書いてある理論だけでは、これは難しかったと思います。
蓼沼:三枝さんのお話で非常に興味深く感じるのは、科学の世界との共通性です。三枝さんはよく"フレームワーク"という言葉を使われていますが、フレームワークとは、物事の本質や構造を理解し、分かりやすく説明するための枠組みのことですね。
三枝:そのとおりですね。

蓼沼:社会科学にせよ、自然科学にせよ、科学が追究しているのは、まさに物事の本質や構造を突き詰めて明らかにすることです。そして学問は、論理性をとことん突き詰めるだけでなく、現場で起きていることの経験やデータと突き合わせて、つねにブラッシュアップしていく必要があります。そうやって磨かれた理論を、逆に現場の人がまた取り込んで考え方をブラッシュアップさせる。つまり、科学の発展とは、理論と経験の均衡点を更新し続ける相互作用であると思います。
三枝:同感ですね。
本質的な言葉を頭の中の冷凍庫に保存するという感覚
蓼沼:では、その実践者である経営者に必要な能力とはどういうものとお考えですか?
三枝:経営者だけでなくリーダー全般に言えることですが、"リード"とは"人より先を行く"という意味ですよね。混沌とした状況の中で、皆がどうしていいか分からずに右往左往している時に「この問題は、こういうことじゃないの?」と整理して、指摘できる能力がリーダーシップの原点です。リーダーのその一言で、皆がモヤモヤしていた混沌が整理され、霧が晴れるようにすっきりとした状況が生まれると、皆は「そうだ、何をすればいいかが見えてきたぞ」と組織的な対応を始める。リーダーとは、それをつねに繰り返せる人であると思います。組織内にそういう存在の人がおらず、ぐじゃぐじゃな状況のまま時間が過ぎて、追い込まれて全員に何となく答えが見えてきた頃になって何かを決めるのであれば、リーダーは後追いの、ただの"決定"をしているに過ぎません。それはリーダーが皆にまだ見えていないことでも機先を制して「本質はこれだ」とズバリ斬り込んで問題解決の要点を示す"決断"とは違います。このように、本質を見極めて断を下すときに必要とされるのが"フレームワーク"だと思います。
蓼沼:そのフレームワークをいくつも持っていて、状況に応じて使い分けられることが大事なのでしょうね。

三枝:私の言うフレームワークというのは、コンサルタントや学者が生み出す複雑なコンセプトとは限りません。もっと広義に、単純な「考え方」でも私はフレームワークと呼んでいます。自分がフレームワークの「引き出し」をたくさん持っていて、この場合はこの考え方が使える、また次の状況では別の引き出しに入っているこの考え方が使えると、その都度、使い分けられるフレームワークをたくさん持っていることが、有能なリーダーが実際に行っている行為だと思います。われわれは経験や座学の勉強の中から、いろいろなことを学び取るわけですが、その学びというのはあまり複雑な話の形ではなく、本質だけを単純な言葉で抜き取って、自分の記憶の引き出しの中にしまっておくことが大切だと思います。それを私はよく"冷凍保存"という言葉で説明します。単純化された本質的な言葉を、頭の中の冷凍庫に保存しておくという感覚です。その冷凍庫の中には、たくさんの言葉が眠っているのですが、中には霜がついて賞味期限の切れたものもある(笑)。しかし、何か新しい状況に直面して、整理がつけられずにウロウロしていると、ある瞬間、「ひょっとして、あの時に経験したあの問題に似ているんじゃないか」と、昔に冷凍保存しておいた言葉に思い当たることがあるんですね。そうすると、自分の冷凍庫の中に残していた記憶や学びの言葉を取り出して、その時はコチコチに凍っているんですが(笑)、その霜を取り払って、つまり「解凍」し、今の状況に当てはめてみる。昔とまったく同じ状況が起きることはありえないので、そのままでは使えないのですが、目の前の問題に適応できるように少し修正してみる。すると、他の人よりも早く「この問題は、こういうことじゃないの?」と言えるようになる。そういう能力があることが、リーダーの本質ではないかと思います。ですから、何か経験したり学んだ時、簡単な言葉で冷凍庫に保存しておく作業が、後々の自分の能力を高めるために大事だということです。たとえば、何か感情的な経験をした場合でも、些末な出来事は捨て去り、固有名詞が出てこないような、いわば抽象化された言葉にそぎ落として、自分の冷凍庫にしまっておく。それがフレームワーク化だと思います。肝心なのは経験話を、些末な話まで含めてまるごと、冷凍しないことです。人間の冷凍庫はあまり大きくないので、すぐ一杯になってしまいますから(笑)。

蓼沼:面白いお話ですね(笑)。経済学の世界でも同様のことがあります。学問のフレームワークには論理的なゆらぎがあってはなりませんが、しかし、当初のフレームワークをつくる作業は、一種の"アート"ではないかということです。論理性よりも、「これが大事」という勘や感性が力を発揮する世界ですね。そしてもう一つは、シンプルに示すことの大切さです。経済学には、ゲーム理論のような人の心理にまで踏み込んでモデル化するものから、一国の経済や世界経済のモデルまでさまざまな単純化のレベルがあります。それぞれの問題に応じて、どのレベルを選び取って当てはめるのか、そこにはセンスが必要であると思います。
三枝:なるほど、理論を生み出すための学者の抽象化作業も同じなのですね。
蓼沼:リーダーは、混沌とした状況の中で、問題解決にぴったり当てはまるレベルで問題の構造をシンプルに示す能力がなければならないということですね。
三枝:それと、問題があるのかないのか、それを嗅ぎ分ける嗅覚みたいなものでしょうか。私はミスミの幹部と話していて、よく「おい、それ臭いぞ」と言うんです。そう言われると、幹部は皆ドキッとする(笑)。本人たちには全く臭わないんですが、私にそう言われると、社長には何か見えているんだろう、自分に見えていない要素って何だろうと、彼ら自身が警戒レベルを上げて、考えるわけです。そこで彼らがゴソゴソと突き詰めていくと、やっぱり問題が隠れていたりする。彼らは人のフレームワークの引き出しを利用して、より賢い意思決定を下す。その分だけ、彼らも賢い経営者人材になっていくわけです。
ミスミを、経営者人材を育成する実験場に
蓼沼:なるほど、フレームワークの重要性がよく分かりました。ところで、三枝さんは2002年にミスミの社長CEOに就任され、2008年以降は会長CEOとしてミスミグループを変革し続けてこられました。社長に就任された際、経営者人材育成をミスミの最優先の経営課題に掲げられたと伺っています。その後、実際に次世代経営者を育成するプロセスで、経営者人材とその育成についての考え方に変化はありましたでしょうか。
三枝:一言で言えば、人を育てることがいかに難しいかを痛感し続けました。ミスミの社長に就任した時、経営目的の第一に掲げたのは経営者人材の育成でした。前にもお話ししたとおり、日本では経営者人材が枯れてしまっていて、それが日本という国の弱点になっていると感じていました。そこで、ミスミを経営者人材を育成する「実験場」にしようと思い立ちました。それが経営者としての一種の野心とでもいうべきものでしたね。社長になると、普通の経営者はまず「業績向上」を語り、その手段としての人材育成です。ところが私は社長になった時、社内外にまず一番目に「経営者人材育成」を語り、その結果として業績向上があるという順番で語りました。ミスミ創業社長の田口弘さんと出会った時、彼はもう歳だから引退したいが後継者がいないと悩んでおられました。それが縁でミスミの経営を引き受けたわけです。
蓼沼:ミスミのトップとして、まずはどういったことから始められたのですか。
三枝:社長に就任する前、自分は何歳になったらミスミから退くかを計算しました。そして、創業社長が引退した年齢に私が達したら、自分も退こうと考えました。当時の私の年齢から逆算して、自分が引退する時には、脂が乗って体力や気力も充実している40代の次世代経営陣にバトンを渡そうと考えました。とすると、その候補者たちはいま37歳から43歳ぐらいまでの範囲の人々が対象になる。就任3か月目に、『日本経済新聞』に「経営者を目指す人は集まれ」という全5段の求人広告を出しました。志ある者はこの指とまれ、と宣言したわけです。
ミスミグループは現在、グローバルで1万人ほどの従業員数に達していますが、私が社長に就任した当時は単なる商社の業態だったので、一部上場企業とはいいながら、社員数はわずか340人程度でした。毎日のように面接をしていました。会社の急成長がすぐに始まり、就任した時は創業40年で売上高500億円の規模でしたが、それが4年で倍の1000億円を超えました。2005年には東証二部上場だった駿河精機株式会社(現株式会社駿河生産プラットフォーム)と経営統合して、それまでの商社機能に加えてメーカー機能も持つ業態への大決断を行いました。その前後から世界展開も積極的に行って、急速に規模を拡大していきました。並行して、経営者人材の育成を手がけていきました。
蓼沼:選りすぐった経営者候補を育成されていったわけですね。

三枝:経営者が育つには、当人が相当なストレッチ(思考や経験の拡張)に努めることが必要です。私は30代で3社の企業再生を手がける中でかなりのストレッチを経験しましたが、リクルーティングを始めてみると、そんな経験を積んでいる人は滅多にいませんでした。私が育成対象にした年齢帯の人々は、大企業ではまだせいぜい課長レベルです。応募してくる人たちはかなり鍛えられているだろうという期待もありましたが、実際には、やはりそれまで会社員の世界に浸かっていた甘さは否めないところがありました。その人々を思い切って事業部長や執行役員という要職に就かせたのです。前の会社ならば、10〜20年後に到達するような職位にいきなり就かせたわけです。ぎりぎり身の丈に合った職位なら、思い切ってジャンプできるだろう、何とかよじ登っていくだろうと。しかし、やはり無理だという人材も少なくありませんでした。そういう場合は下の職位に降りてもらってやり直させるといいのですが、降格はキャリアに傷がつくので実際にはできません。そのまま「期待に添えませんでした」と辞めていく者も少なくありませんでした。「ミスミは退職率が高い」と批判された時期もありました。それは悩ましいことでしたが、しばらくして「私の志はあくまでも経営者人材の育成にある。出ていく人より残って頑張っている人を励みにしよう」と割り切って、続けたのです。そんな時期が4、5年くらい続きました。やがて、その中から次世代を託そうと思える人材が出てきましたね。



階段を上がっていく人には必ず"熱き心"がある
蓼沼:経営者候補の募集に応募した方々ですから、自信もおありだったろうと思います。ポジションやチャンスを与えてチャレンジさせるという育成方法を取られたのですね。
三枝:大企業は次世代の経営者を50代に達してから抜擢する場合が多いですが、私はそれでは遅すぎると思っていました。40代からトップ経営者として勝負してもらう必要がある。私のマンツーマンの指導だけでなく、やはり社内には育成する仕組みが必要です。ミスミには、毎年「ビジネスプラン(事業戦略)」を作成させるシーズンがあり、経営者人材が自部門の事業戦略の作成に挑むストレッチ訓練を全員に課してきました。私自身が戦略研修講座を開き、それを受けてからその作業に当たってもらいました。当初は戦略の組み立てに馴れていませんから、彼らのビジネスプランには甘い部分がたくさんあって「却下」と言われてやり直しを命じられることも頻繁に起きました。本人たちは必死に考えてまたプレゼンする。これを繰り返すわけです。そして、そこそこのレベルになった時に「よし、これでいい。承認」と言われると、彼らは脱兎のごとく、その実行に飛び出していくわけです。苦労してつくっていますから、自分の計画は完全に頭に入っています。しかし、計画どおりに1年間運ぶ事業など一つもありません。必ずどこか崩れます。では計画づくりに意味がないかというと、そんなことはありません。必死になって考え抜いているからこそ、崩れた時にいったいどこがおかしいのか、本人がいち早く気づくわけです。だからそれを修正する行動も早くなる。この12年間、ミスミの業績が大きく向上したのは、こうした仕組みがあったからだと確信しています。
蓼沼:なるほど。フレームワークを使って事前に考え抜くからこそ、想定からズレた時の対応が早くできるということですね。その考え抜いた経験の積み重ねが、経営者人材の育成には欠かせないのでしょうね。
三枝:面白い現象があります。ある事業部長が4年前にミスミに来た直後に作成した事業計画書を自分で引っ張り出して見たら、当時、なんて幼稚なものを書いていたんだろうと思って、恥ずかしくなったという笑い話です。この話には二つの意味があります。一つは、彼が4年間で経営者人材としてそれだけ成長したということ。そしてもう一つは、そんなレベルでも当時、会社としてOKを出していたという事実です。つまり、最初からいきなり高いレベルは求めていない。徐々に成長すればいいというスタンスでした。
蓼沼:一橋大学のゼミと全く同じですね(笑)。ゼミを4年間やると、入学したばかりの学生と卒業間近の学生とは取り組むレベルが違います。2年、3年と徐々に上のレベルを目指して向上させていく。まさに一橋大学の教育そのものだと感じました。
三枝:なるほど(笑)。そして、肝心なことがあります。リーダーシップを発揮するには、論理性とフレームワークが必要ですが、実はもう一つあるのです。"熱き心"です。人生で階段を上がっていく人には、必ず"熱き心"があります。
蓼沼:分かります。
三枝:自分から取りにいく姿勢といいますか、リスクテイクを増やしていく。チャレンジしようという志があるということです。そうすると自分が新たなフレームワークを獲得することも加速されるわけです。
もっと荒っぽさや野心といったものも必要
蓼沼:大学でも、論理的思考力と"熱き心"をともに備えた若き人材を育成したいと思います。三枝さんには「一橋シニアエグゼクティブプログラム(HSEP)」において多大なるご協力をいただいているほか、以前から本学の非常勤講師として学士課程やMBAで教鞭を執っていただいており、2005年からは客員教授としてご活躍です。これから本学を巣立ち、各界でリーダーシップを発揮していくことが期待される現在の学生たちをどのように育成すべきとお考えでしょうか。
三枝:私が学生だった頃と違って、最近の学生は非常に素直でよく勉強すると感じています。しかし、私は何か物足りないものも感じています。私が問題にしている、経営者人材が枯渇しているという日本の風潮が、今の学生の世代にも及んでいるのではないかと感じることがあります。素直でよく勉強する学生は、自分に課されたことはきちんとやるわけですが、昔よりサムライが減っている感じなのです。就職先を見ると、今でもエスタブリッシュメントの大企業が並んでいますね。非常に優秀な一橋の学生は、これからの日本を背負って立つ人材だと思います。そんな人材には、もっと荒っぽさや野心といったものも必要ではないかという気がしています。それと、これからは国際性を身につけることが必須ですね。昨年、学部の一年生に大教室で講義をした時には、学生から250通もの感想文が来たのですが、私の話を聞いて、自分の人生を将来どうもっていくかをこれまで考えていなかったという反省を書いた学生が多かった。アメリカの学生の多くは、人と同じことはしたくない、なるべくユニークな人生を送りたいと考える風潮が強い。彼らは親からそうけしかけられています。アジアの若者もハングリーです。一方、日本の親はなるべく安全な道を歩くように教育する人が多い。私はそこに問題を感じています。

蓼沼:90年代頃から学生気質は徐々に変化して、今ではかなり真面目になっていると私も感じています。授業に出て学ぶこと以上のものをもっと求めてほしいと思いますし、いろいろな面で経験を積んでほしいものです。学びの先に何があるのか、さまざまな可能性や選択肢が見えてくれば、チャレンジする心も湧いてくるのではないかと思います。現在でも、中には途上国の開発支援を志して積極的に海外でのインターンに出ていくような学生もいます。そういう意欲のある学生がたくさん生まれるような雰囲気をつくっていきたいと思います。
三枝:一橋大学が理念として掲げてきた"キャプテンズ・オブ・インダストリー"という言葉なのですが、私が学生の頃、実は古臭いと思っていたのです。しかし今は非常にいい言葉だと思いますし、まさにこの国に求められていることです。そして私は世界の中で明日の日本を元気にするには、さらに"キャプテンズ・オブ・ザ・ネイション"、つまりこの国のリーダーの輩出が求められていると思います。
蓼沼:どうもありがとうございました。
(2015年10月 掲載)