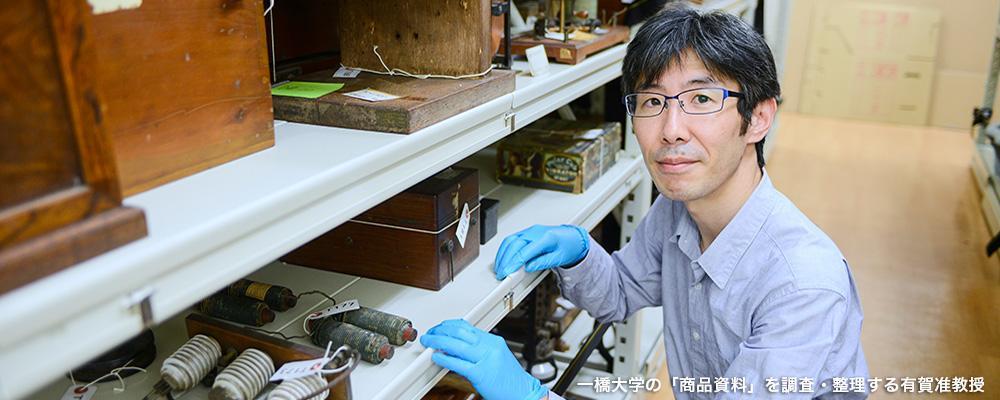前提を問い直す人文学の手法で、科学技術の歴史にアプローチする
- 言語社会研究科准教授有賀 暢迪
2022年12月27日 掲載

有賀 暢迪(ありが・のぶみち)
2005年京都大学総合人間学部卒(物理科学専攻)、2007年京都大学大学院文学研究科修士課程修了(科学哲学科学史専修)、2010年同大学院文学研究科博士後期課程研究指導認定退学。2017年博士(文学)(京都大学)。2009年日本学術振興会特別研究員などを経て2013年国立科学博物館理工学研究部研究員、2020年同博物館理工学研究部研究主幹を経て、2021年一橋大学大学院言語社会研究科准教授に就任、現在に至る。専門分野は科学技術史、博物館学。
力学、シミュレーション、博覧会...広がり続ける研究テーマ
私の専門は科学史です。主に「物理学・数理科学の歴史」と「近現代日本の科学技術史」、2つの領域で研究を行っています。同時に、言語社会研究科が提供する「学芸員資格取得プログラム」を西洋美術史の先生と共同で担当しています。もっともそれは「結果的にそうなった」と表現するべきかもしれません。今でこそ言語社会研究科で教育・研究を行っていますが、京都大学文学研究科での研究、国立科学博物館での資料調査や展示制作など、さまざまな外的要因に導かれてここに至っているからです。そのプロセスの中で私の興味・関心は広がり続けていったため、現在の研究テーマも多岐にわたります。
たとえば、ニュートンやオイラーの著作に基づいて力学の誕生と発展を考究する「力学史」。20世紀後半のコンピューター・シミュレーションの発展について、歴史的な考察を行う「計算科学史」。明治時代から現代までの、「日本の物理学の教育・研究の歴史」。科学技術に関する展示を通して、科学・技術と社会の関わりを考察する「博覧会史・博物館史」......。これらの多種多様な研究テーマに共通しているのは、「過去の文献や資料を探して読み、解釈し、表現する」という姿勢です。その意味では、対象こそ科学・技術ですが、アプローチは人文学と言えるでしょう。
また歴史を研究するためには、資料が適切に保存され、いつでも利用できる状態になっていなくてはなりません。そのため研究者の個人文書や実験機器、さらには本学の文化資源である「商品資料」などの「資料保全とアーカイブ」にまで、私の興味・関心は広がっています。そして、目一杯広がった研究テーマにどう取り組んでいるかと言えば、「その日の気分でテーマを選ぶ」ということになります。正確には、その日の授業や用向きによって都度、軸足を置き換えることが私なりのスタイルです。
高校で理系を選択し、大学院で「文転」。科学史の研究へ
高校では理系クラスを選択し、大学では物理学を主専攻に選びました。しかし私は当時から、理系・文系に関係なく幅広い勉強がしたいと思っていました。また、自分で新しい発見をしていくことよりも、理論や概念について「何故そう考えられたのか」という背景に関心がありました。そのため授業の選択には迷いが生じ、他学部のシラバスを見て経済学部の授業を受講したこともあります。その中で、京都大学では文学部にあった「科学哲学科学史専修」の授業を受け、すっかり魅了されたのです。そこで大学院に進学し、いわゆる「文転」を果たしました。
大学院の修士課程と博士後期課程を通じ、私は18世紀のヨーロッパにおける力学の歴史を研究しました。このきっかけとなった指導教員の授業では、数学者オイラーの論文を取り上げ、フランス語の原文を音読して訳すという作業をしていたのですが、どうしてもわからないところが出てきます。私はフランス語を履修していて、力学の基礎知識も持っていましたが、1回の授業で読み進められるのは1〜2ページが限界でした。しかも科学史の研究に求められるのは、単に原文を日本語に置き換えることではありません。原典が書かれた当時の科学の常識を踏まえ、著者の論旨を正確に理解することなのです。ということは必然的に別の論文や本を、しかも場合によってはラテン語やドイツ語で書かれたものも読まざるを得ません。その結果、博士論文はオイラーを軸に18世紀の力学全体を再考するという、哲学史・思想史に近い内容になりました。
その後、転機が訪れます。東日本大震災による福島第一原子力発電所の事故は、科学の歴史を研究してきた私には衝撃でした。現在の科学は何故このような事態を引き起こすようになったのか、歴史的な過程を知り、理解しなければならないと強く感じたのです。
ヨーロッパから日本へ、科学から技術へと踏み出した国立科学博物館時代
この「転向」のあと、私は国立科学博物館で研究員として働くことになりました。もともと大学院生の頃から個人でWebサイトを作り、科学史を一般向けに紹介していた私は、展示・講座など普及活動への興味・関心があり、応募したのです。その結果運よく採用されたのですが、8年間の勤務を通して、日本の科学者や研究機関に関する資料を調査・整理するという全く新しいスキルを修得することにもなりました。また、国立科学博物館では昔のことだけでなく、最先端の科学の内容も展示に取り込まねばなりません。そこで私は現代を、特に戦後の日本を科学史研究の対象とする機会も得ました。18世紀ヨーロッパの力学で博士論文を書いた研究者が戦後日本を対象にするということは、ふつうは考えられないでしょう。
国立科学博物館では、18世紀ヨーロッパの原典から近現代日本の一次資料へと踏み出すと同時に、科学史から技術史にも興味・関心を広げることになりました。そもそも博物館、あるいは博覧会ではモノ、特に人工物を扱うわけですから、研究者はそこに存在する技術に目を向けざるを得ません。しかも古代の車輪なども技術の一種なのですから、技術史の射程は科学史よりも広く、社会との距離は科学史よりもはるかに近い。これまでご紹介してきた研究とはさらに異なる知識やスキルが求められます。はじめに「さまざまな外的要因に導かれてここに至っている」とお伝えしたのは、このような経緯があったからです。
もしかしたら、一つに絞って研究を深めるほうが、研究者としての評価は上げやすいのかもしれません。しかしすでにお伝えしたように、私は学部生の頃から「理系一択」という絞り込みができないまま、さまざまな出会いや転機によってここまで来ています。一つに絞ることには根本的に向いていないのでしょう。
言語社会研究科は、一度立ち止まって人文学を学びたい人に最適な環境
言語社会研究科で学ぶ方々は、さまざまなバックグラウンドを持っています。私の研究室のゼミ生でも、学部で哲学を専攻したあと修士課程で本研究科に来て科学史を始めた人、理系から他大学の修士課程に行って科学史を学び、現在は災害をめぐる歴史学に興味を持っている人、高校で物理の教師をしていて原子力に関心を持ち、科学史を学びに来た人など、目的は人それぞれです。共通しているのは研究において「人文学のアプローチをとる」ということでしょう。人文学のアプローチとは、世の中の前提を問うことです。科学技術にしても、現状をそのまま前提にしていくのではなく、一度立ち止まって「その前提は何なのか?」を問う。それが人文学の仕事だと私は考えています。
科学史は基本的に私の授業でしか学べないという制約はありますが、本研究科には人文学のさまざまな分野で研究を行う先生方がいらっしゃいます。科学史のアプローチに不可欠な人文学の思考や語学をきちんと学びながら研究したい人にとっては、非常に有用な環境であると私は考えています。また、モノと向き合うことから始めて物事の意味を問い直し、再構築して発信する一連のスキルを身につける「学芸員資格取得プログラム」もあります。単位を揃えるのは大変ですが、このプログラムで吸収できるものは大きいでしょう。そもそも自らの前提を一度立ち止まって考え直したいという人には、ぜひ門を叩いてほしいですね。(談)