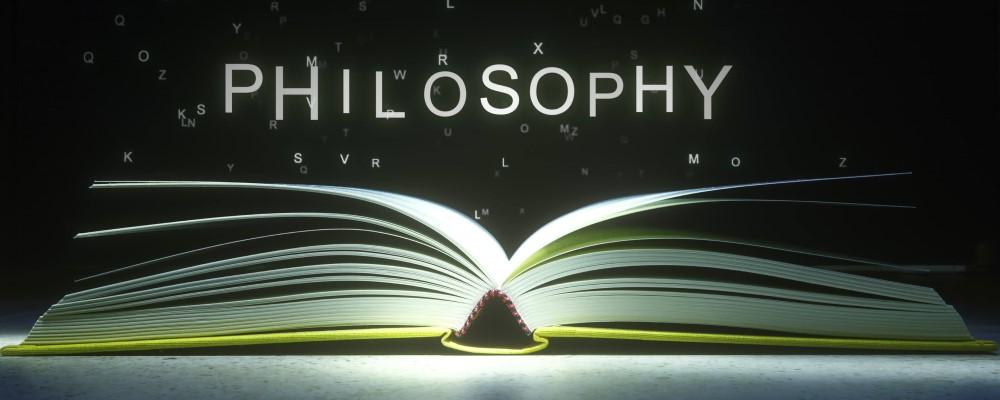隠された大きな前提を見逃さず、顕在化させる法哲学
- 法学研究科教授安藤 馨
2021年12月22日 掲載

安藤 馨(あんどう・かおる)
2004年東京大学法学部卒業。2006年同大学院法学政治学研究科修士課程修了。専攻は法哲学・道徳哲学。2006年から同研究科助手・助教を経て、2010年 神戸大学大学院法学研究科准教授、2020年 同教授。2021年より現職。著作に『統治と功利』(勁草書房)『法哲学と法哲学の対話』(有斐閣、大屋雄裕と共著)など。
原理に遡ったうえで幅広い分野にアプローチする研究スタイル
私の専門である法哲学には、「悪しき法にも従うべき道徳的義務はあるか?」という有名な問いがあります。
この問いに答えるためには、まず「悪し、とは何か?」を理解するために、道徳哲学や倫理学に遡る必要があります。すると今度は「そもそも道徳とは何か?」を問うメタ倫理学に遡らざるを得なくなる。さらに「世界には道徳が存在するのか?」という形而上学へ。そして「正しい、良いと言うとき、私たちは何をコミュニケートしようとしているのか?」を取り扱う言語哲学の深淵を覗きこむことになるのです。
このようにできるだけ異論の余地のない原理に遡り、そこから議論を始めることが、私自身の哲学的スタイルです。原理にまで遡ると、もともと哲学の外部に置かれていたさまざまな現実世界の問題と原理的に一貫したやり方で向き合えます。その結果、特定の一大テーマと言うよりは「AIの統治」「死の害と死後の害」「世代間正義」など幅広い(といえば聞こえはいいですが、要は雑多な)トピックをカバーするという点で多少ともユニークな法哲学者というポジションを占めるようになっているのではないかと思います。
実定法の授業に違和感を持ち、法哲学(正義論)のゼミを選択
法学については高校の頃から興味を持っていました。ちょうどロースクールが開設されることが決まった時期だったこともあり、大学→ロースクール→法曹界という進路をイメージしていました。
ただ、裁判官と検察官については敬遠する気持ちがありました。両親が裁判官や検察官として勤務しているような友人たちがいたのですが、その大変さが伝わってきたからです。当たり前のように転勤があり、日常生活での制約も多い。そんなストレスフルな状況で、他人の人生を左右する裁判に携わるのは、自分には無理だと思いましたから、「じゃあ弁護士かな......」という程度の動機付けで大学に進学しました。
大学3年生になる頃、自分は法学不適合者なのではないかと感じるようになりました。2年生から始まった、裁判所の判例など、一定の時代・社会においてのみ実効性を持つ「実定法」の勉強にはまったく馴染めませんでした。個別の判例や学説に接するたび、論理的に導き出されるはずのない結論に違和感しか持てない。大半の学生が何の疑問も持たずにその結論を受け入れている。「ついていけない」と思いました。「非論理的」は言い過ぎだとしても、何らかの前提を隠し、目の前に空いているはずの「穴ぼこ」を飛び越えるように話を進めようとする空気に、疑問を感じざるを得ませんでした。
そこで学部3年生からのゼミでは法哲学を志望しました。法哲学は「法とは何か」を研究する法概念論と、「法がいかにあるべきか」を研究する正義論に分かれていますが、当時開講されていた法哲学のゼミは正義論を扱うもので、実定法が嫌いになりかけていた私は迷わず正義論のゼミを選択しました。その結果、自身が法哲学研究者になってしまうなどとは、当時はむろん思ってもいなかったのですが。
結果が見えないのであれば、ルールを作るべきではない
ゼミの指導教員は、井上達夫教授(現・東京大学名誉教授)で、当時リチャード・アレン・ポズナー(アメリカの法学者・連邦巡回区控訴裁判所判事)が唱える「法と経済学」をテーマにしていました。科学化を目指していた経済学が、実定法学に馴染めなかった当時の私には――その馴染めなさを私は実定法学の「非科学性」のせいだと思っていたのですが――とてもポジティブなものに映りました。経済学が法学と結びつくと、立法後の結果をある程度予測できると感じられたことも、ゼミを選んだ理由でした。
あるルールを立法化した場合、「人の動きはこうなるだろう」と予測を立て、「したがって結果はこうなるから立法化すべきである/すべきではない」と導き出す。結果を重視し責任を持つ立場、言い換えれば、結果が見えないのであればルールを作るべきではないとするポズナーの立場(ごく広く言えば功利主義ということになります)に、私はシンパシーを持ちました。
「法と経済学」が活かされた有名な事例は、借地借家法の改正です。もともと同法は、物件を貸す側の賃貸人に対して「弱い立場にある賃借人を保護する」という目的で施行されました。しかし結果として、物件の流動性を下げる原因となり、家賃が上がって賃借人の経済的負担が増す、貧困層に対する物件供給が滞るなどの事態を招くことになりました。目指していたはずの目的、つまり弱い立場の人々を保護する、ということをむしろ妨げる法律になっていたわけです。
この問題は経済学からの指摘で明らかとなり、賃借人が無期限に占有することがないように法改正が行われています。このような事例からも、法学と経済学の垣根を下げ、結びつけることは重要だと言えるでしょう。
「等しいものは等しく扱わねばならない」という、誰もが合意できる前提
指導教員である井上達夫教授の著作に出会えたことも、大きな収穫でした。井上の『共生の作法』(1986年サントリー学芸賞受賞)という著作を読んだ私は、単なる好悪の感情を超えて、「正義」を学問の対象として語り得るのだことを知り、鮮烈な印象を受けました(いまでは私自身は同書の主張の多くが間違っていると考えるようになりましたが、それでも機会があればみなさんにはぜひ一読してみて欲しいと思います)。
同書の中核的主張を簡単にまとめればこうなります。「正義」の研究にはさまざまな立場やアプローチがありますが、どれが正しいかという議論に軸足を置くとどうしても相対主義に陥ってしまいがちです。しかし、「等しいものは等しく扱わねばならない」という、誰もが正義の中核として合意できる(しばしば無内容だと思われがちな)前提をまず認めること。そうすると、私たちが「それはおかしい!」と腹を立てる事例の殆どは、等しいものを等しく扱っていないというもの、自分(と身内)に甘く他者に厳しいという態度、すなわちエゴイズムや依怙贔屓の産物であることが分かります。言い換えれば、「正義」についての具体的な議論に立ち入る手前で、実は私たちが「正義」(または「不正義」)の問題だと思うものの殆どの事例を扱えるのです。
同書を読んだ時、得た印象は「ああ、そうだったのか!」という実に鮮烈なものでした。相対主義に陥ることなく「正義」を合理的に論ずることができるのだ、というわけです。法学の「非科学性」を嫌悪していたはずなのに、よりによって哲学(それも道徳哲学)に関心を持ったのは不思議だと思われるかもしれません。しかし、哲学の中でも私がその末席に連なっている(と自分では思っている)「分析哲学」と呼ばれる流儀では、実定法学にしばしば見られるように明瞭に空いている「穴」を無視して議論を進めることを(それこそが私の最初の不満だったわけですが)良しとしません。また、現在の私は正義論を含む道徳哲学が、自然科学などと本質的に異ならない「科学的」営為であ(りう)ると考えています。振り返ってみると、やはり大学初年次に出くわした問題が現在の自分を強く規定していることに気が付かされます。
世の中の議論は、かなり大きな前提が隠された状態で行われてしまう
正義論における議論は、根本的な部分ですれ違ったまま対立することが珍しくありません。
たとえば、ロバート・ノージックとジョン・ロールズという2人の哲学者の有名な対立があります。表面的には「福祉国家を批判すべきか/擁護すべきか」が対立点とされていますが、実は違うのです。そもそも、古典的なリバタリアンであるノージックと、再分配的でリベラルなロールズという立場の違う2人が結論において相容れないのは当然のこと。両者の真の対立点=隠された大きな前提は、煎じ詰めると正義の中心的な焦点が、個人の行為にあるのか、それとも、経済・社会制度にあるのか、についての対立なのです。聖人でもない限り、平等主義的再分配を日常生活の一挙手一投足の場面で実践すべきだ・他者に強いてでも実践させるべきだと思っている人はいません。にもかかわらず、なぜ社会制度については、そうした平等主義的再分配が(国家的に強制されることすら)正しいと思うのでしょうか。対立の核心は実にこの点にあります。
正義論に限らなくても、基本的に世の中の議論は、かなり大きな前提が隠された状態で進められることが多いです。そして前提が隠されてしまっていることによって議論は対立したまま不毛にすれ違い続けます。人類はそうした対立を21世紀にいたるまで何千年も繰り返してきたと言っても過言ではないでしょう。だからこそ、隠れた前提は何か、彼我の真の対立点はどこにあるのかを考えることは、実定法を批判的に学ぶうえで避けて通れないトレーニングだと私は考えています。ある学説が実はまったく説得力のない隠れた前提に依拠している、ということはままあることですから。
一橋大学生の皆さんには、結果を出せるポリシーメイキングにこだわってほしい
一橋大学で正義論に関する授業を行ううえで、私は学生の皆さんに、どの正義論が正しいかについてコミットしてもらうつもりは――もちろんコミットするのは自由ですが――ありません。むしろ前述のように、「その議論はそもそも成り立っているのか」「隠れた前提は何か」「真の対立点はどこにあるのか」などを批判的に見つめる視点こそを身につけてほしいと考えています。
授業では、概ね「分析哲学」と呼ばれる方法に従って言葉の定義を一つひとつ積み上げていくので負担は軽くないはずですが、他者の議論をフェアに扱い真の対立点を見出すトレーニングこそが、「等しいものは等しく扱う」という正義の態度の獲得につながります。それは、将来のポリシーメイカー候補である皆さんにこそ獲得してほしい資質です。そして、社会に出たら、法学と経済学をともに学ぶ一橋大学の学生らしく、政策の因果的結果を見落とすことのないポリシーメイキングにこだわってほしいと願っています。(談)