地域政策、都市政策に潜む《不思議》を見つけ出し、社会科学の視点から問題の本質にアプローチする
- 社会学研究科准教授堂免 隆浩
2014年秋号vol.44 掲載
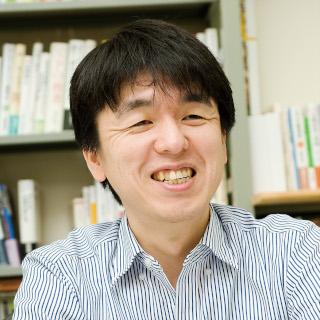
堂免隆浩
博士(工学)を、東京工業大学大学院で取得。1997年広島工業大学環境学部環境デザイン学科卒業。1999年東京工業大学大学院社会理工学研究科社会工学専攻修士課程、2004年同博士課程修了。東京工業大学大学院社会理工学研究科助手、助教を経て、2008年一橋大学大学院社会学研究科専任講師、2011年同准教授、現在に至る。
都市工学から社会科学の視点へ環境デザインへのアプローチを転換
「豊かな環境のデザイン」という場合、これまでその主役は都市工学でした。都市計画をつくったり、建築物を建てたり、都市工学の専門家こそが、豊かな環境をつくることができると考えられてきました。しかし、都市工学の専門家がとらえる豊かな環境とそこで暮らす人、その施設を利用する人の望みに、私は少なからずギャップを感じていました。また、都市工学による問題の解決方法は対症療法的な傾向があり、本質に迫るためには、ほかのアプローチもあるのではないかと思うに至りました。
そこで私は環境のデザインにかかわる問題に、社会科学の切り口でアプローチし、解決につながる知見を手に入れようと研究に取り組んでいます。なかでも、「住環境の保全と住民の自己組織化」や、「公共施設管理と行政・市民の関係」、「非営利組織(NPO法人など)とまちづくり」など、地方自治体と住民の関係が主なテーマです。
たとえば、以前に『住環境保全を目的とした住民自治組織による紛争予防の取り組み』(玉川地域における近隣住民と建築主等を仲介する事例を対象として)という研究を行いました。閑静な住宅地の景観を壊されたくない近隣住民。人気エリアのブランド力を活かして、大きなマンションや商業施設を建てたい建築主。両者を仲介するために、住民自治組織がーー規制や管理を行う行政とも連携しながらーーなぜ自主ルールを導入できたか、どんな落としどころを見出したかについて掘り下げました。
また、練馬区で唯一サッカー利用が許されている「練馬区立みんなの広場公園」の事例では、区の条例では一般に禁止されているサッカー利用が、なぜこの公園に限って可能なのかを調べました。練馬区まちづくり条例を施行している行政と、見回り・見守り活動などの自主管理に乗り出した住民の関係から、その地域ならではの落としどころを発見できます。
住環境や公園などのハード面だけではなく、住民同士の連携による取り組みなど、ソフト面での政策にも注目しています。たとえば、商店街の空き店舗をどうするか?という問題。これは、日本のどの商店街にもあてはまる難問です。これまで空き店舗には、利益を出す商店の出店が期待されてきました。これに対し、ある商店街では、子育て拠点づくりに取り組むNPO法人が空き店舗を利用しています。商店街は住宅地のなかにあるので、NPOの活動にとって商店街は好立地です。一方、商店街にとっては、拠点を訪れるお母さんがついでに買いものをしてくれます。このように、なぜ商店街とNPOが協力できるのかを考えることも、まちづくりでは重要であることが分かります。
利便性や効率性だけで判断するのではなく社会全般に対する学びを地道に重ねる大切さ
環境のデザインにかかわる問題に、都市工学ではなく社会科学の切り口でアプローチする。この方法をとるようになったきっかけは、学生時代にあります。
私は大学院で都市工学を専攻していました。都市計画や建築、行政のスペシャリストを育成する学部です。演習では、一人ひとりがバーチャルでつくった都市や建築物について意見交換をします。「この都市のデザインは良い」「この建築物は悪い」という意見を聞きながら、私はふと違和感を覚えました。
都市工学では、いわゆる上うわもの物をつくる際の前提として、利便性や効率性に価値が置かれます。しかし「良い・悪い」を決めるうえで、その前提は果たして適切だろうか......という疑問が、頭をもたげてきました。つくった後、誰が使うのか?、周辺への影響は?など、利用者や生活者の視点が必要ではないだろうか。その場合、利便性や効率性だけでは「良い・悪い」を判断できないのではないか。都市工学はとても重要な学問ですが、それだけでは足りない、社会科学全般を広く学ぶ必要があるという結論に至ったのです。
そこで専攻は専攻として学びを深めながら、同時に、社会学、心理学、経済学など、いわゆる社会科学の分野にも学びの対象を広げるようになりました。今思えば、その頃から私のなかには「interdisciplinary(インターディシプリナリー=学際的、さまざまな分野の専門家が協力し合うこと)」というキーワードが芽生えていたようです。
縁あって現在は一橋大学の社会学研究科に籍を置いていますが、この環境は本当にありがたいと感じています。社会学研究科にはあらゆる専門分野の先生方がいらっしゃるので、私が研究テーマを掘り下げるうえでさまざまな知見を得られます。自分の専門分野のなかで閉じてしまっていたら気づかなかっただろう、と感じる瞬間が多々あり、文字通り学際的な環境です。
この環境にあって、私が最も影響を受けたのは、問題へのアプローチ方法です。直面する問題の本質に迫るとき、社会科学(特に、社会学)における問いの立て方はとても参考になります。都市工学では、「どうすれば良い環境をつくれるか?」という手段に着目した問いを立てます。これに対し、社会学では、「なぜ良い環境がつくれているのか?」という問いを立てることになります。「なぜ」という問いを立てれば、問題の発生原因に注目することができるようになります。事例のリサーチやフィールドワークを地道に積み重ね、なぜを問うというアプローチであるべきなのです。一橋大学で研究を進める日々のなかで、私はそう確信するようになりました。
「interdisciplinary」の環境を活かした、思慮深いゼネラリストを育成
せっかく「interdisciplinary」の環境があるからこそ、私は学生に、問題の本質に迫る姿勢を持ってほしいと考えています。そして本質に迫るために、「まず《不思議》を探し出そう」と話しています。具体的には、《不思議》発見のワークショップとして、ゼミの学生たちと一緒に街を歩き、自分なりの《不思議》を見つけてもらう。「なぜこんなことが起きているのだろう」「なぜこういうことができているのだろう(または、できていないのだろう)」という視点を持つわけですね。そして持ち帰った《不思議》をみんなで発表し合い、検証し、2種類の《不思議》に選別します。自分が知らないだけですでに社会的に解決されている《不思議》と、実はほかの人も感じていた社会的な《不思議》。後者は、学術的常識を反証できるかもしれない《不思議》の種ですから、ここでの選別はとても大切です。
ただし学生同士では、いくら今までの知識を総動員しても、どちらの《不思議》なのか判断がつかない場合もあります。そんなときこそ、「interdisciplinary」の環境を活用すべきなのです。研究室にこもっているのではなく、研究室の外に出て、各分野の先生方に質問をぶつけていけば良いと思います。私がそうであるように、学生もきっと幅広い知見を得られるはずですから。
これは、学生生活の過ごし方に限った話ではありません。一橋大学の学生は社会に出てから、プロジェクトを取りまとめるポジションにつく可能性が高い。プロジェクトには、さまざまな部署や業界のスペシャリストが集まるでしょう。そのような場では、スペシャリストの能力を引き出したり、スペシャリスト同士を橋渡ししたりするゼネラリストの存在が不可欠です。しかも、一面的な知識や考え方に依らない、思慮深いゼネラリストがーー。一橋大学の卒業生にはそんなポジションをしっかり引き受けてほしいと思います。そして、思慮深いゼネラリストになるために、「interdisciplinary」の環境を活かした学生生活にしてほしいですね。(談)
(2014年10月 掲載)

