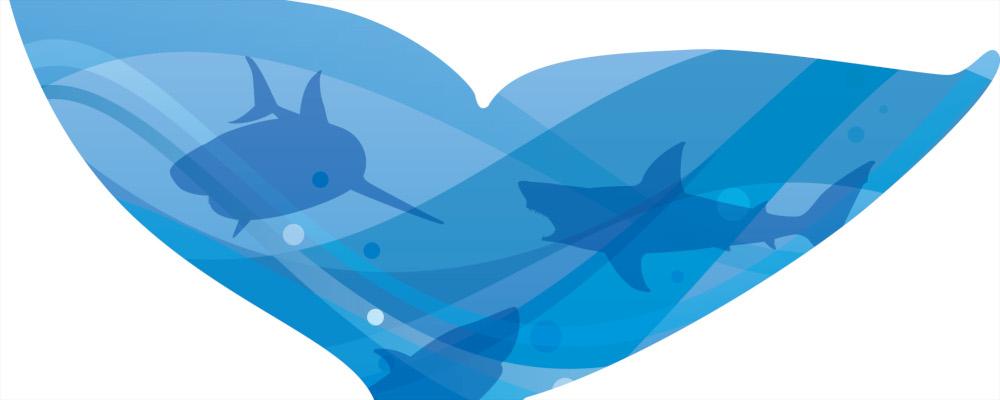「食」は、もっとも身近な国際問題。 現場から、多様な価値観を世界に提示したい
- 社会学研究科教授赤嶺 淳
2015年秋号vol.48 掲載

赤嶺 淳
1996年、フィリピン大学大学院にて博士号(フィリピン学)を取得。1997年以降は「ナマコ」を研究課題として活動を続ける。2001年より名古屋市立大学人文社会学部で教壇に立ち、2007年にはワシントン条約日本政府代表団顧問に就任。2014年に一橋大学大学院社会学研究科(地球社会研究専攻)教授となり現在に至る。専門は「海域世界論」「食生活誌学」「フィールドワーク教育論」。主な著作に『ナマコを歩く──現場から考える生物多様性と文化多様性』(新泉社、2010年)、『クジラを食べていたころ──聞き書き
高度経済成長期の食とくらし』(編著、グローバル社会を歩く研究会、2011年)、『バナナが高かったころ──聞き書き 高度経済成長期の食とくらし2』(編著、グローバル社会を歩く研究会、2013年)、『グローバル社会を歩く──かかわりの人間文化学』(編著、新泉社、2013年)等がある。
机上のイデオロギーではなく、人びとの営みにこそ答えがある
私の研究活動は1992年、大学院生として留学したフィリピンを舞台に始まりました。フィリピン研究を志すきっかけになったのは、独自のアジア研究を提示した故鶴見良行氏の『バナナと日本人ーーフィリピン農園と食卓のあいだ』(岩波新書、1982年)でした。バナナの生産から流通、消費という一連のプロセスを克明に辿り、日比間に存在する格差と不平等を訴えた名著です。出会ったのは、1985年にプラザ合意が発表され、円高の恩恵を受けながらバブル絶頂期を迎えた日本が、アジアをはじめとした海外との距離を一気に縮めていく時期でもありました。「机上で語られるイデオロギーからではなく、人びとの日常生活から、アジアと日本の関係性を考えていくべきだ」
そんな鶴見氏の姿勢に共感し、日常的に消費しているモノからアジア史を見た時の広がりや面白さに興奮したことを覚えています。以来、私は身近な「食」というモノに焦点をあてることで、生産地社会と消費地社会の関係性を明らかにしてきました。具体的には、「人類はいかに自然を利用してきたのか」を主な研究課題として今日に至っています。
社会を変革するためには、現場を「見る」「聞く」「歩く」こと
食の中でも「ナマコ」との関わりは、私のライフワークとなっています。発端は1997年、フィリピンの離島であるマンシ島を訪れた時に受けた衝撃です。南シナ海に集団で出漁し、1カ月間も船上生活をしながら操業するナマコ漁で経済的な繁栄を謳歌している。そんな噂を聞き、訪問したその日からフィールドワークを始めたのです。ナマコ漁に従事するマンシ島民の声を聞き、彼らの生活を記述していきました。
転機の一つとなったのが、2002年に行われたワシントン条約締約国会議で議論されたナマコの国際貿易規制です。グローバルで画一的な管理を求める環境保護団体と、ローカルに蓄積されてきた資源利用の実践は、どう調和されるべきなのか、近年の研究課題にもなっています。
足かけ20年に及ぶ研究の成果は、『ナマコを歩くーー現場から考える生物多様性と文化多様性』(新泉社、2010年)にまとめました。タイトルの「歩く」には、研究成果の還元を通じて、社会を変革していきたいという「能動」的覚悟を込めています。
全世界を納得させるグローバルスタンダードがない問題
昨年、新たな「食」の研究を本格的にスタートさせました。それは、「クジラ」や「サメ」の問題です。フカヒレに限らず、世界には、サメ肉を食べる地域がある一方で、サメを食べることを「野蛮」視する人もいます。1970年代以降に世界的潮流となった反捕鯨の文脈と通じるものを感じています。
クジラに関しては、「捕鯨は伝統であり、鯨肉食は国民文化である」というのが日本の主張です。実際、食糧難に喘いでいた戦後復興期には鯨肉が命をつないでくれたわけです。1987年度を最後にミンククジラなどの商業捕鯨は一時停止となりましたが、条約の規制を受けないクジラやイルカは商業的に流通しています。また、調査捕鯨の副産物としての鯨肉も流通しています。ただ、日本全体で考えると、現在口にしているのは1人あたり年間50グラムに届きません。これはハンバーガーのパテ2個分にも満たない分量です。「動物福祉」「動物の権利」といった倫理観が市民権を得ている欧米の環境NGOから、「果たして国民食と言えるのか?」という批判が出るのも分かります。
他方、文化という側面から考察すると、"お正月の必需品"といった伝統が根づいている地域があるのも事実です。捕鯨が盛んだった地域には"鯨の墓"があったり、供養まで行われていたりします。しかし、仏教的な宗教実践とキリスト教的な価値観の相違もあって、供養という行為は全地球的に理解される思想でもありません。
国民食だから守りたいという考えも理解し難いし、だからと言って文化的マイノリティーを切り捨てようとするのも早計にすぎます。この問題に、全世界を納得させるグローバルスタンダードはないと思います。しかも、一見、豊かに見える私たちの食卓も、そのほとんどを海外からの輸入食材に依存しているという現状からしても、「野蛮」という批判を受けたから食べないと簡単に結論を出してよいのか疑問を感じるわけです。だからこそ私は「クジラ」と「サメ」の問題に取り組み、時間をかけて思考していきたいのです。
"グレーゾーン"の中にある多様な価値観を明らかにしたい
近年では、政治にしても、なんにしても、分かりやすいことが良しとされる傾向にあります。あまりにも問題が複雑怪奇に関連しあっていて、人びとは考えるのが面倒くさいと感じているのでしょうか?
しかし、グローバリゼーションが進めば進むほど、「風が吹けば桶屋が儲かる」的な物事の関連性を見通す力が必要とされます。
"白か黒か"、"0か1か"といったデジタルな答えを出そうとしているわけではありません。それは個人が判断すれば良いことです。この研究で目指すところは、地球上には"グレーゾーン"とも言うべき多様なアナログ世界があることを明らかにし、それを選択肢としたうえで、みずからの"生き方"を選んでもらうことにあります。「食べる」という日常的な選択を通じ、さまざまな問題群を思考するきっかけとしてもらいたいのです。
活動はすでに始めています。その第一歩として現在行っていることは、かつて商業捕鯨に関わった人びとを訪ね、その生活を丹念に記述し、人びとの生きてきた歴史を日本社会の変化の中に位置づけていくことです。捕鯨船の砲手さん、クジラを解剖する人、鯨肉の問屋さん、支えたご家族......対象は多岐にわたります。
ちなみに、最終的にまとめる本は英語で書こうと決めています。世界中の人びとに広く読まれ、提言できるものにしたいからです。タイトルは『Eating Whalesand Sharks』(クジラとサメを食べる)。ただ、シドニー・ミンツさんという食人類学の大家に相談すると、「"日本人がまたなにか言っているぞ"と受け取られかねないから、副題を付けたほうが良い」とアドバイスされました。そこで、『History of Questionable Foods』(微妙な食の歴史)と添えるのはどうかと考えていたりしますが、著書が完成するのは、少なく見積もっても10年は先になるでしょう。
論争が絶えない問題ですし、高度に政治化した現状の中で打開していくことが難しいことは覚悟していますが、消費者の1人として自分も納得できる結論を提示したいと思っています。人びとの生活を豊かにしていくグレーゾーンの重要性を再確認するためにも。(談)
(2015年10月 掲載)