民法の根源を考え、フレキシビリティを獲得するための「背信的悪意者排除論」
- 法学研究科教授石田 剛
2018年冬号vol.57 掲載
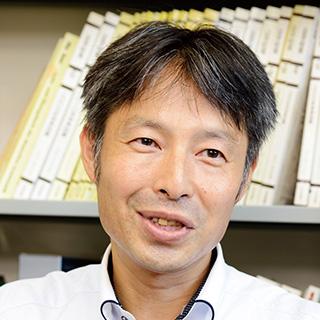
石田 剛
法学研究科教授、博士(法学)(京都大学)。1990年京都大学法学部卒、1995年京都大学大学院法学研究科民刑事法専攻、博士後期課程単位取得満期退学。1995〜1996年京都大学大学院法学研究科助手を務めた後、1996年立教大学法学部専任講師に就任、1998年同大法学部助教授、2006年同大法学部教授に就任。2007年同志社大学大学院司法研究科准教授を経て、2008年同大大学院司法研究科教授に就任。2011〜2015年大阪大学大学院高等司法研究科教授を経て、2015年より一橋大学法学研究科教授に就任、現在に至る。2014年より信託法学会理事を務める。
財産をめぐる私的トラブルについて
根源的な問題をつねに見つめ直す
民法は、私たちの日常生活のほとんどすべてに関わる法律として、とても幅広い分野をカバーしています。日常生活に関わる私的トラブルは、大別すると、「家族」にまつわるトラブルと、お金・土地・建物など「財産」をめぐるトラブルに分けられます。
私の研究対象は主に後者です。日常生活において遭遇するさまざまな財産に関するトラブルをどう処理すべきか?という問題。その問題を解決するための基本的な枠組みを考えること、言い換えると「根源的な問題をつねに見つめ直すこと」が、私の研究テーマです。財産をめぐるトラブルとしては、不動産などの契約に関わる紛争や、交通事故の損害賠償に関わる紛争などが挙げられます。特に最近では、知的所有権などの無体物に関するトラブルも増えており、取引において重要な位置を占める財産のありようも変わりつつあります。
しかし、仮に対象物の性質が有体物から無体物へと変わっても、問題の根源が同質であるがために、社会の変化に関係なく維持される部分は必ずあるのです。その根源は、歴史的背景をさかのぼってみたり、他の国・地域の法と照らし合わせてみたりと、多面的にとらえる作業の中で見えてきます。それを探り、他の法律領域にも応用可能なフレキシビリティを得ること。私が一橋大学で社会科学を研究する根幹は、そこにあると言えます。
「自由」「競争」を重要視する法秩
序両者の関係をめぐるモヤモヤを解消したい
基本や根源にこだわっているのは、そもそも私自身が発展的な現象、現代的な現象にあまり興味を持てないからです。流行りものに鈍感、とも言えます(笑)。また、小学生の頃から歴史が好きだったこともあり、つねに、より「その根源にあるもの」に意識が向くのです。それは法領域に対しても変わりません。
たとえば契約においては、「自由」と「競争」が重視されます。「自由」と「競争」なくして、活発な経済活動や社会の進歩はあり得ないという考え方が現代の私法秩序の基本です。では「自由」「競争」とは何なのか。どう定義し、実際の私的トラブルを前にしてどう解釈すべきか。本当に、これらは絶対的に重要なものなのか。モヤモヤ感が残ります。法の歴史をさかのぼると、「自由」と「競争」をそれほど重視しない社会の実例はいくらでも見出すことができます。同時代的に見ても、たとえば英米法や大陸法(ドイツ・フランスなど)と照らし合わせると、「自由」や「競争」といった価値に対するウエイトの置き方には社会ごとにバラつきがあり、絶対的に正しい均衡点は存在しないのです。
このように私法秩序の基本をなす概念や考え方に光を当て、法制度の来歴や他国の法状況を調べながら、財産をめぐるトラブルを通して社会を観察し、社会の発展に微力ながら貢献することが民法研究の存在意義だととらえています。
「背信的悪意者排除論」の考察
(1)法律学が定義する「悪意者」とは何か
私が研究を始めて以来現在まで、最も関心を寄せているテーマの一つが、「背信的悪意者排除論」です。この法理は、民法第一七七条における「第三者」の解釈論として形成された考え方です。
※民法第一七七条「不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない」
この法理の意味を理解するには、「悪意者」、とりわけ「悪意」とは何かについての説明が必要です。法律学で言う「悪意」とは、日常用語のように、良からぬたくらみを秘めたという意味を含んでいません。端的に「知っているか」「知らないか」という事実認識のレベルで、「知っている」ことを「悪意」と言います。たとえば、Aが所有する不動産をBに売却したことをCが「知っている」場合。Cは「悪意者」とされます。このことは、民法第一七七条における「登記をしなければ、第三者に対抗することができない」という規定を解釈する際にとても重要です。
先ほどの例に即していえばA・B間の不動産取引において、通常、Cは取引に直接関わらない「第三者」です。A・B間に不動産売買契約が成立すると、BはAから不動産の所有権を取得しますが、そのことを登記しておかなければ、A・B以外の「第三者」に対してBは所有権を取得したことを主張することができない。民法第一七七条はこのように定めています。「第三者」が善意か悪意かを条文の文言は問うていません。そこで、「第三者」に当たるCは、悪意者であっても、Bの所有権取得が登記されていない場合、その不動産を依然としてAのものと扱うことが許されます。Cが、Bよりも良い取引条件(より高額の売買代金の支払)を提案してAと二重に契約を結び、登記を済ませたら、その不動産はCのものになります。横取りではないかと思われるかもしれませんが、民法第一七七条を文言どおり適用すればそうなるのです。
このように「悪意者」を「第三者」に含める解釈の背景には、正当な競争行為を通じてAから不動産を取得したCは、社会的にみてBよりもその不動産を有効利用できる可能性が高いから、その権利取得を認めるのが望ましい、という評価があります。そう言われると、Cは確かに悪意者だけれど、「負けても仕方ないかな」とBも一応納得するかもしれません。しかし、Bが到底自らの負けを甘受できない特殊な「悪意者」が現れた場合にどうするか、がさらに問題になります。そこで「背信的悪意者排除論」という法理が考え出されました。
(2)背信性や信義則をどう定義すべきか
「背信的悪意者」とは、どのような者を指し、「背信的悪意者」に当たると、民法第一七七条の解釈においてどのような扱いを受けるのでしょうか。
背信性について、民法では「信義則に反するもの」と定義されています。Cが不動産を入手した目的や経緯に照らして、民法第一七七条に基づく主張をすることが「信義則に反する」場合、その行為は背信的であるとされ、Cの権利は認められず、Bの権利が保護される──これが「背信的悪意者排除論」であり、この場合、民法第一七七条の適用はされません。
たとえば、CがA・B間の取引に立会人として参加し、売買契約が結ばれたとします。Cは取引の当事者ではありませんが、取引に関する情報をすべて把握しています。その立場を利用して、Bの登記が未了であることに乗じて、CがAから二重に同じ不動産を買い受けたとします。Cは、BがAから権利を取得する際の証人として、自らBの権利取得を積極的に容認する行為をした以上、その後で、登記未了を盾にとって、Bの権利取得を否定する態度に出るのは、「矛盾行為」として信義則に反すると判断されます。
あるいはBが権利取得の登記をしようとしていたところ、Cが、Bを脅迫したりだましたりして登記を妨害したなど、違法な手段を用いてBの登記具備を妨害したのであれば、そうした不当な介入行為をしたCがBの未登記を非難するのは、同じく信義則に反します。
いずれの事例も「背信的悪意者」に当たることにつき共通理解が形成されています。もっとも、限界事例に目を向けると、信義則違反に当たるか否かを限界づける明確な指標はありません。専門家の間でも評価が分かれており、実際におきた紛争事例の集積をまって、「正当な競争行為の範囲内とは言えない」事案の類型化作業を行っている段階です。こうした作業を進めてゆくと、必然的に「自由」や「競争」とは何か、どう解釈すべきか?という問いに突き当たります。自由主義社会の中では、誰と誰がどんな契約を結ぼうと確かに「自由」です。ではその契約を結ぶための「競争」はどこまで許されるのか。背信的悪意者排除論の研究においては、こうした根源的な問題と向き合わざるを得ないのです。
民法の基本中の基本を考え、他の領域にも柔軟に応用するための「思考のフレーム」
背信的悪意者排除論が形成された戦後の高度成長期に比べると、不動産取引の紛争事例はやや少なくなってきました。しかし、「背信的悪意者排除論」は、民法における基本中の基本を考える素材として、他の取引をめぐる紛争にも応用が可能な抽象度の高さを備えています。
民法も、現に生きているわたしたち人間相互間の利益調整のためのルールですから、条文の文字どおりの意味を金科玉条化することなく、実情に合わせて適切な解決を模索することが重要です。同時に民法学の責務として理論的体系化の筋道を探り出していかなければなりません。根源までさかのぼり、対象物に左右されない思考のフレームを持ち、柔軟に適用していくことは、すべての法律家にとって重要なことですから。(談)
(2018年1月 掲載)

