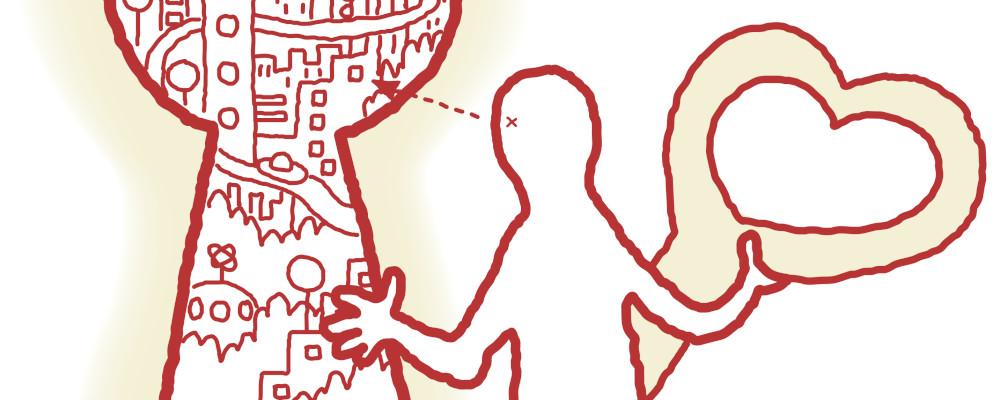あたかも消費者がモノを買うように投票する有権者
- 社会学研究科教授中北 浩爾
2013年春号vol.38 掲載

中北 浩爾
1968年三重県生まれ、1991年東京大学法学部卒業、1993年同大学大学院法学政治学研究科修士課程修了、1995年同大学大学院法学政治学研究科博士課程中途退学、1997年博士(東京大学・法学)取得。立教大学法学部教授などを経て、2011年4月より一橋大学大学院社会学研究科教授。著書は、『一九五五年体制の成立』(東京大学出版会)『日本労働政治の国際関係史』(岩波書店)『現代日本の政党デモクラシー』(岩波新書)など。
変わる日本の政党デモクラシー
自分の気に入ったモノを購入した消費者が、期待外れだったり、ほかにもっと気に入ったモノが現れたりしたら買い替えてしまうのは珍しいことではありません。これが市場競争であり、企業は消費者の選択を求めて、価格や品質などで他の企業と競い合っています。この競争と選択のメカニズムが正しく機能するならば、消費者と企業の双方に望ましい効率的な状態になるとされています。
消費者が自由に商品を買うかのように、有権者が選挙で政党を選んでいるのが現在の日本のデモクラシーです。勝者総取りの小選挙区制のもと、激しく競い合う二大政党がマニフェストを掲げる。有権者は固定的な支持政党を持たず、政策本位で投票する。いわば有権者は消費者であり政党は企業。政策(マニフェスト)が商品で票がお金と考えれば、まさに票と政策の交換であり、消費者の購買行動と有権者の投票行為が重なってみえます。こういう民主主義モデルを「市場競争型デモクラシー」と呼ぶことができます。
その形成プロセスは、1994年の政治改革に始まります。非自民非共産の8党派からなる細川内閣のもとで政治改革関連4法案が成立。これにより衆議院の選挙制度として小選挙区比例代表並立制が導入されました。マニフェスト導入の前提となるのは、①小選挙区制に基づく二大政党制、②中長期的に支持する政党を持たない無党派層、③首相を中心とする政治主導です。1994年以降も続けられた政治改革によりこれらの条件が整い、2003年にマニフェスト選挙が始まりました。2009年の自民党から民主党への政権交代は、その成果でした。
実は、それ以前は、「参加デモクラシー」の時代でした。大学紛争が激化した1968年は、高度成長に伴う社会変化や矛盾が顕在化した象徴的な年とされます。そこから、エコロジーやフェミニズムなど、「新しい社会運動」が起こりました。その一環として既存の代議制民主主義のあり方を変革すべく登場したのが、参加デモクラシーです。草の根の市民参加による直接民主主義を復権しようという動きで、選挙における政党間の競争こそが民主主義だという考え方を批判したのです。そのインパクトは自民党や社会党にも及び、一般の党員に党首選挙の投票権を与える制度が導入されました。
このように民主主義には多様なモデルが存在し、社会の雰囲気や価値観などに対応して変わってきたのです。
小選挙区制の問題とは何か
先の2012年末の総選挙は、小選挙区制の問題点をあらわにしました。比例代表の得票率で27・6%に過ぎない自民党が、61・3%の議席を獲得し、圧勝したからです。確かに、これではたして民主主義といえるのだろうか、という疑問がわき起こってきますが、このような小選挙区制の効果は、導入されたときからすでに予想されていました。
しかし、そうだといっても、2005年の郵政選挙での自民党の大勝、2009年の民主党の圧勝、そして今回の自民党の勝利と、大きな議席の移動が生じており、それは当初の予想を超えるものです。前回の総選挙における民主党の比例代表の得票率は42・4%でしたが、今回は15・9%です。いかに浮動票が増えているかがわかります。その変動が小選挙区制によって増幅されているのであって、これでは政党が安定的に人材を育成したり、中長期的な観点から政策を立案したりすることが難しくなります。
固定的な支持政党を持たない無党派層の増大は、人々の価値観の変化だけでなく、小選挙区制を導入した結果でもあります。かつては、財界寄りの自民党と労働組合を基盤とする社会党といったわかりやすい図式がありました。野球の巨人ファンと阪神ファンのように、簡単には乗り換えられないものでした。しかし、小選挙区制によって雑多な勢力を寄せ集めて二大政党が作られたため、違いが小さくなり、選挙のたびに投票する政党を変える無党派層が増えたのです。
無党派層だからこそ、しがらみなく政策本位で政党を選択できると考えられたのですが、内閣支持率の乱高下や総選挙ごとの振り子現象を引き起こしています。小選挙区制によって作られた二大政党は、民主党に典型的にみられるように、まとまりを欠き、内部対立を繰り返してきました。有権者の二大政党に対する不信の一因はそこにあり、2010年の参議院選挙以来、みんなの党や日本維新の会などの第三極が台頭しています。
アメリカやイギリスといった小選挙区制を採用している国々の二大政党は、日本と比べるならば、社会的な基盤をしっかりと持っています。アメリカでは共和党が南部と西部、民主党が東部と太平洋岸を地盤とし、イギリスでは保守党が南部、労働党が北部で優勢です。あらかじめ当選者が決まっているような安全議席が少なくなく、一部の地域の票をめぐって選挙戦が戦われます。
日本が不安定な政治を脱するためには、政党と有権者をどう近づけるかが重要になります。有権者の間で根強い政治不信は、選挙という瞬間でしか政党とかかわらないことが大きいと思います。どうやって、政党が党員やサポーターを増やし、中長期的に支持してくれるような有権者を獲得できるか。小選挙区制の見直しも、その一環として行われる必要があるでしょう。
「可能性の技術」としての政治
これまで政治を社会と関係づけて考えることが大切だとお話ししてきましたが、それと同時に、政治の面白さが政治家のリーダーシップにあるのも事実です。「政治は可能性の技術である」というビスマルクの有名な言葉があります。政治的行為とは、複数存在する選択肢のなかから一つを選び出す行為です。自らを取り囲む状況を固定的ではなく、可変的なものとしてとらえ、さまざまな可能性を探りながら、最良の選択をしていく。できれば可能性の幅自体を広げていく。こうした行為が政治です。「これ以外方法がなかった」という言葉は、政治家には禁句です。
たとえば、小泉政権の郵政選挙。局面を打開し可能性の幅を広げたいい例です。郵政民営化法案が参議院で否決され、これで終わったと思われた瞬間、衆議院の解散を断行したうえで、郵政解散というフレームを作り上げ、造反者に「刺客」を擁立する。そして、大勝して、郵政民営化を実現しました。小泉首相が進めた新自由主義的改革には批判も強いのですが、不可能と思われたことを可能にしたリーダーシップのあり方は、政治がまさに「可能性の技術」であることを示しました。
社会学部に政治学がある理由
一橋大学では社会学部のなかで政治学を教えています。多くの大学では法学部に置かれていますが、これは東大モデルです。東京大学法学部は国家官僚を育成する目的で創設されたため、法学とともに政治学を置いています。旧帝大をはじめ多くの大学が、それを踏襲しています。また、早稲田モデルでは、政治経済学部という括りで、政治学は経済学と結びついています。
一橋大学は旧商科大学であり、国家よりも産業界など社会に有為な人材を送り出す使命を持っています。そして、第二次世界大戦後、法学社会学部を法学部と社会学部に分ける際、政治学が社会学部に所属することになりました。こうした歴史的な経緯を背景として、一橋大学では、統治のための国家学としてではなく、社会学・哲学・教育学・歴史学などと連係しながら、市民社会の学問として政治学が教えられています。
現代の政治は、社会のさまざまな領域との連関を意識しつつ、幅広い視点で分析されなければなりません。永田町や霞が関よりも、市民の目線から政治をとらえる。それが社会学部に政治学がある意味であり、使命であると考えています。(談)
(2013年4月 掲載)