逆境を、創造を灯す光に。
- 津田塾大学 学長髙橋 裕子
- 一橋大学 学長中野 聡
2022年7月1日 掲載
2024年度に発行される新5千円札の肖像に採用された津田梅子。6歳でアメリカに留学した際、現地で津田ら幼少の留学生たちをサポートしたのが、日本国の初代駐米公使を務めた森有礼であった。後に津田塾大学と一橋大学の建学者となる2人の出会いから150年経った今、両大学の学長が、津田ら我が国における女子教育の先駆者たちの足跡をたどりながら、その歴史的意義や今日にまで残る課題、一橋大学への期待などについて語り合った。

髙橋 裕子(たかはし・ゆうこ)
津田塾大学学芸学部英文学科卒業。筑波大学大学院(国際学修士)、アメリカ・カンザス大学大学院にてM.A.及び Ph.D.を取得。桜美林大学専任講師・同助教授を経て、1997 年から津田塾大学助教授、2004年から同大学教授。2016 年より同大学学長。専門はアメリカ社会史(家族・女性・教育)、ジェンダー論。
著書に『津田梅子の社会史』(玉川大学出版部、2002 年、アメリカ学会清水博賞)等。International Federation for Research in Women's History会長、ジェンダー史学会副代表理事、アメリカ学会元会長、日本学術会議会員、日本私立大学連盟常務理事、国立大学法人東京工業大学経営協議会委員、内閣府男女共同参画局男女共同参画推進連携会議議員、日米教育委員会日本側委員、公益財団法人大学基準協会常務理事、公益財団法人アメリカ研究振興会常務理事。
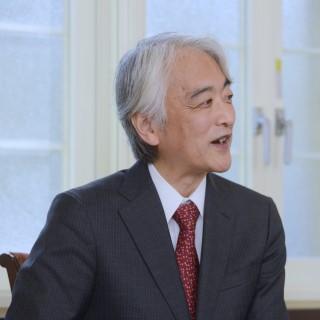
中野 聡(なかの・さとし)
1983年一橋大学法学部卒業。1990年一橋大学大学院社会学研究科博士後期課程単位取得退学。1996年博士(社会学・一橋大学)。研究分野は地域研究、アメリカ史、フィリピン史、日本現代史。1990年神戸大学教養部専任講師、同大学国際文化学部専任講師、助教授を経て、1999年一橋大学社会学部助教授、2003年同大学大学院社会学研究科教授を歴任。2014年同大学大学院社会学研究科長、2016年同大学副学長を経て、2020年一橋大学学長に就任。
津田梅子との関わりは"不思議な縁"

中野:津田塾大学は2020年に創立120周年を迎えました。そして、2024年度からの、新5千円札の肖像に津田梅子が採用されました。期せずして新1万円札は渋沢栄一なので、そこでも津田塾大学と一橋大学のつながりを感じさせられます。髙橋先生は津田塾大学の学長であり、津田梅子研究者でもいらっしゃいますが、新紙幣の件はどのように受け止めておられますか?
髙橋:私が津田梅子を研究するようになったことや、2024年3月までの本学学長の任期中に津田が新紙幣の肖像に採用されたことには、いずれも何かの縁を感じています。
中野:髙橋先生が津田梅子研究を始められた経緯とは?
髙橋:私は、本学の学芸学部英文学科を卒業後、アメリカの女性史やジェンダー史に関心があったので、1980年に筑波大学大学院地域研究研究科修士課程に進学し、2年次にカンザス大学大学院歴史学研究科へ留学し、M.A.を取得してから筑波の修士課程を修了しました。その後、カンザス大学大学院教育学研究科の博士課程に進みました。主にアメリカの女性史、家族史、子ども史を学びましたが、7校の名門女子大学、いわゆるセブンシスターズなど、女性の高等教育について関心を持っていました。博士論文のテーマを決めなければならなかった数年前の1984年に、津田塾大学本館の屋根裏部屋で津田梅子の440通あまりの膨大な書簡が発見されたのです。博士論文のテーマを決めたのはその数年後でしたが、その知らせに接した際に、セブンシスターズの一校であるブリンマー大学で学んだ津田が多くのアメリカ女性の支援を得て、日本に女子英学塾を建学し、女子高等教育に大きな役割を果たしたことをアメリカの社会史の視点からとらえ直してみようと思い立ちました。そこで、アメリカから津田塾大学に戻り、その書簡を読み込むところから津田梅子の研究を始めたという次第です。その書簡は、たまたま1984年に本学を卒業した学生たち何名かが、最後に学内を探検しようとして発見したものでした。
中野:ほう、そうだったんですね。
髙橋:書簡の整理が終了した時期に博士論文の構想を練りつつ書くタイミングを迎えていたという偶然の出合いがありました。また、1989年末の帰国後、桜美林大学の専任講師や助教授を経て1997年に本学に戻った際、2000年の創立100周年記念事業委員会の委員となり、資料室の改修や記念論文集の出版に関わって、津田塾大学や津田梅子のことを内側に入っていろいろと学ぶ機会を得たことも一つの縁です。2016年に学長を拝命し、2019年の春頃に新紙幣への採用が決まったということも、すべて「不思議な縁」があったとの思いです。さらに言えば、新紙幣採用決定で『津田梅子~お札になった留学生〜』というテレビドラマ(テレビ朝日)がこの3月に放映されましたが、そのエグゼクティブプロデューサーが本学の卒業生で、いろいろと協力させてもらいました。そんなところにも縁を感じています。
津田梅子が成し遂げられた要因
中野:日銀が発行した紙幣における女性の肖像としては、樋口一葉に次いでの採用となりました。ジェンダー研究者としてはどう感じていますか?
髙橋:これまで女性が採用された例としては、最初が明治時代の1円紙幣の神功皇后で、次が紫式部、樋口一葉です。後の2人は文学者ですが、津田梅子は教育者であり、支援者を集めての起業家でもあるという違いがあると思います。しかも、起業した女子英学塾は津田塾大学となって今日まで122年間も続いています。
津田の起業には大きな意義があります。一般的なケースとは違い、人、もの、資金、情報の多くをアメリカから集めていったことです。財閥系企業などの男性からの協力を断ることこそしませんでしたが、頼ることもありませんでした。なぜならば、当初から自らの教育理念は当時の日本の男性には必ずしも理解されないだろうと考えていたからです。そこで、海外に大きく頼ることにしたわけです。何もかもが発達している現代とは違い、明治期にあっては、相当な労力を要したであろうと思います。
中野:そのとおりだと思いますね。津田梅子がそれだけ大変なことを成し遂げた一番の要因とは、どういったことだとお考えですか?
髙橋:まずは、アメリカでネットワークをしっかり築いたこと。そして、日本とアメリカという二つの文化の間で生きた経験が大きかったと思います。津田は18歳になる直前の1882年に留学を終えて帰国し、1885年から官立の華族女学校で英語を教えるようになり、1889年から3年間、再度の留学をします。帰国後、再び華族女学校での教授を経て、1898年からは女子高等師範学校の教授も兼務しました。こうした中で状況を見極めながら自らのミッション、成し遂げられることを考え、1899年に高等女学校令と私立学校令が公布されるや、1900年に官職を辞し、二つの学校を辞任して女子英学塾を創立します。
この間、当時の制度をつくった明治のエリート男性の良妻賢母をよしとする考え方とは相容れないものを津田は持っていました。女性は生まれながらにして男性が取り組むような仕事には向いていないと思われていた中、女子英学塾はそういう考え方に与しないと、静かに、しかしはっきりと、表明したわけです。
何度も乗り越えた危機

中野:コロナ禍の影響で一年遅れで開催された、昨年10月の120周年記念式典で、髙橋先生は学長挨拶で「津田は何度も危機を乗り越えた」と話しておられましたね。本学の場合は、森有礼が1875年に建学した商法講習所が、渋沢栄一の協力を得るなどして、様々の苦労や変遷を経て1920年に官立の東京商科大学に昇格するわけです。それが大きな通過点となって現在の一橋大学につながりましたが、この間何度も危機を乗り越えてきたと伝わっています。
その危機の一つが、1923年の関東大震災を契機とする、神田から国立へのキャンパス移転です。当時としては大事業でしたが、震災のわずか4年後に兼松講堂が建っていますので、相当なスピードであったろうと思います。こうした当時の実行力を思うにつけ、成長が停滞している今の日本と比べて改めて感嘆します。
貴学としては、どういった危機があったのでしょうか?
髙橋:関東大震災は本学も同様で、五番町校地、麹町の校舎が灰燼に帰しました。授業は近くの女子学院の校舎を借りて早く再開できましたが。その際、津田梅子の右腕となったアナ・C・ハーツホンがすぐアメリカに戻り、3年かけてファンドレイジングを行うのです。ロックフェラー財団を含めて50万ドル、現在の7億8,000万円ぐらいを集め、これをもとに現在の小平の本館等を建てました。
中野:当時、復興支援が海外から多く集まったと言われていますが、それにしても凄いですね。支援金を出すほうにも思いがあったのだろうと思います。
髙橋:そうですね。日米関係が悪化しつつあった当時、アメリカ政府の対日方針に賛成しない人が震災の状況を見て、特に女性に対して手厚くサポートしようとの気運があったと本学の元学長で歴史学者の飯野正子先生が書いておられます。
中野:1920年に、世界大戦の反省から生まれた国際連盟の精神を達成する目的で国際連盟協会が設立され、渋沢が初代会長に就任しました。戦前の日本では最大の平和運動と言われていますが、1920年代はこうした民間外交で日米関係をいい方向に持っていこうという動きがあったわけですね。しかし、20年後に太平洋戦争に突入してしまいました。
髙橋:本学の第3の危機が、その太平洋戦争です。その前の第2の危機は、1929年に津田が64歳で亡くなったことです。2代目の塾長に就任した星野あいは、女子英学塾を卒業後、津田が設けた「日本婦人米国奨学金」に応募してブリンマー大学に留学し、帰国後に女子英学塾の講師になります。その後、1919年に教頭となって津田を支えました。震災を津田とともに乗り越えましたが、津田の死後、1931年に現在の小平に校舎を移し、1933年に女子英学塾から亡き創立者を顕彰するためにその名を冠した津田英学塾に校名変更します。
数学科のルーツ

中野:そんな矢先に太平洋戦争が起こるわけですね。
髙橋:英語が敵国語となり、学校名に「英」の字が入っている、英語教員を養成する学校を志願する学生がどんどん減っていきました。高等女学校では英語科目が必修ではなくなり、授業時間も減らされてしまったからです。英語教員を養成する学校としてどう生き残っていくか、非常に大変な時期であったろうと思います。生き残りを図るため、違う学科を設けようと史学科や国文科の新設を文部省に申請したところ、理科系でなければだめだと却下されました。そこで、1943年に理科を設けることにしたのです。数学科と物理化学科があり、志願者161名の中から58名が入学しました。この年に、校名から「英」の文字を外して「津田塾専門学校」に改称しました。そして戦後の1948年に新制大学として昇格して「津田塾大学」の設立が認可されたわけです。
中野:今日でも数学科があるのが、貴学の大きな特徴ですね。そのルーツは戦争にあったと。
髙橋:理科の新設で何とか生き残ることができました。結果的に、早くから女性が理科の力を身につけるという、とても創造的な営みになったわけです。そこから、「逆境を、創造を灯す光に。」という本学のミッションステートメントの一文が生まれています。
中野:なるほど。戦争の時代といえば、東京商科大学も「商」は軍事統制経済に相応しくないと文部省から指導が入り、1944年に「東京産業大学」にやむを得ず改称しました。学内では猛反発があったそうで、終戦後の1947年に東京商科大学に戻しています。その後、1949年に新制大学への移行に伴って現在の一橋大学に改称しました。今年の入学式では、ウクライナ情勢もあるので、太平洋戦争のときのことについて話しましたが、当時の大学生は文系が軍隊に取られる比率が高く、理系・医系をもつ帝国大学が30%程度であったのに対して本学では約80%に上りました。結果的に、本学の学生から多くの戦没者が出てしまいました。どの大学にとっても卒業生は最大の財産であり、これは残念なことでした。戦地から生還した卒業生たちが、戦没学友に対する思いを胸に、戦後復興を支える人材として活躍してきたことも、本学の歴史の重要な一コマだと思います。
変革を担う女性の育成

中野:津田塾大学も数々の凄い人材を生んでいますね。たまさか私は貴学で2007年から2013年まで非常勤講師を務めさせてもらいましたが、自立心に富んだとてもユニークな卒業生を送り出していると知りました。
髙橋:教育方針として、「変革を担う、女性であること」をモットーに、何かを変えていく推進力となることをエンカレッジしています。個性が強く、尖っている存在となることを推奨する大学と言えますね。
中野:そのモットーは建学時からのものですか?
髙橋:建学の頃は、そもそも女性の高等教育は不要と考えられていましたから、女性は大学だけでなく旧制高校にも入ることができませんでした。リベラルアーツ教育は女性には不要と考えられていた時代にあって、リベラルアーツ教育も専門教育も提供したいと願ったことが女子英学塾の建学の精神です。つまり、国内にそういった発想がなかった中、創立者自身が変革を担っていたと言えます。そして卒業生に対し、女性を抑圧していた制度やルールを変えていくことを期待したわけです。その流れの中で、官房長官や外交官、都市銀行支店長、経団連副会長など「初の女性〇〇」という、文字通り変革を担う人材を輩出してきました。私はよく「女の長い列」と言っているのですが、次世代の道を切り拓いた先達の背中を追いながら、卒業生はその道をさらに広げていく役割を果たしていると思います。しかも、122年という歴史がありながら、本学の卒業生は3万5000人ほどです。私立大学にはこの瞬間に4万人の学生が在籍しているところもある中、まさしく少数精鋭と言えるでしょう。
中野:素晴らしいですね。
髙橋:2017年には総合政策学部を開設しました。先頃、第2期目の卒業生を送り出したところです。
中野:どういった学生が育ちつつありますか?
髙橋:新しいことにチャレンジしていく進取の気性のある学生が育っていると自負しています。話はちょっと逸れますが、先ほど危機を乗り越えた話がありましたけれども、一橋大学の危機を救ったのは全員男性ですね。
中野:それは認めざるを得ませんね。
髙橋:本学の場合は、ほぼ全員が女性です。女性たちが中心になってこうした危機を乗り越えられるというストーリーを学生に語れることが、本学の強みであると思っています。
中野:他学にはない強みでしょうね。
髙橋:私は11代目の学長ですが、歴代の学長も1名を除き全員女性です。このことも、他の女子大にはないことです。中野先生がおっしゃるユニークな人材が多いということの背景には、女性に対して「女性もいろいろなことがやれるのだ」というメッセージを発していることがあると思います。
ジェンダーギャップの課題

中野:本学は、髙橋先生がご指摘のとおり戦前は完全に男の大学で、戦後になって初の女子学生が入学しました。そこから時間をかけて徐々に増やし、現在では学部で約3割と、文系ということもあって国立大学の中では比較的高くなっています。とは言え、まだまだジェンダーやダイバーシティの課題は山積みです。大学に残る男性中心的な文化やバイアスを変えていかなければいけませんし、そのうえで、新しい一橋大学らしさやユニークさを備えて社会で活躍する女性の卒業生がますます増えていくことが重要だろうと思っています。
一方、女子大には女子大としての意義があると思いますが、どのように考えていますか?
髙橋:女性が常に中心に置かれていることですね。入学式などで語るとき、男性の存在を考えず、女性だけを意識して話すことができるところが共学との違いでしょう。
日本では、いまだに女性が社会のマージナルなところに立たされていますね。ジェンダーギャップ指数は、とりわけ政治・経済分野において圧倒的に低く、先進国の中で最低レベルです。社会の中心で活躍する立場に立つ女性が少なすぎるという現在の状況を常に意識して話し、女子学生をエンパワーできることが、女子大であることの意義ではないでしょうか。
中野:ジェンダーギャップ指数がG7の中で著しく低いという状況の中、大学における教育というものを考える必要があるでしょう。その文脈の中に、女子大としての津田塾大学の大きな役割があると思います。
髙橋:日本の大学に入学する学生はほぼ男女半々に近づいてきましたね。しかし、大学の教員は全く半々とはなっていません。学生が大学で同じ性別の人がどういう活躍をしているのかを見るとき、日本の高等教育機関は女子学生に十分な期待感や自尊感情を与える場にはなっていないということです。本学の場合、教授もほぼ男女半々、学部長は男女1対1です。事務部門を含め、責任ある立場に女性も就いています。ジェンダーの視点からどのような「大学の風景」を学生に見せているかを女子大学も共学大学も意識する必要があります。学生に対する教育的な見地からも取り組んでいかなければならないと思っています。いずれにせよ、日本の高等教育界も圧倒的に男性優位社会であることが大きな課題ですね。
中野:先日、この『HQ』で本学の卒業生であるサッポロホールディングスの女性の人事担当役員である福原真弓さんと対談をしました。ビール業界初の生え抜き女性役員に就任したという人です。その対談の中で、学生の女子率約3割をはじめ、教授や経営協議会メンバーなどの女性比率が他の国立大学より比較的高いものの、外部から招へいした人材ばかりで内部登用者がいないことが問題という話をした次第です。
ジェンダーロールの克服へ
髙橋:生え抜きをどれだけ登用していくか、言うは易し、でも行い難い問題ですよね。女子大でも全部が全部できているわけではありません。女子大の女性学長は、日本は約30%ですがアメリカでは90%と大差がついています。アメリカでは、女子大の役割が十分把握されているからこその90%だと思いますが、そもそも女子大の存在意義はそういうところにあるのではないかと思っています。
中野:自分自身、本学には優秀な学生が集まり、約3割の女子も男子と全く同様に活躍しているとの実感がありますが、今のお話を聞くと日本社会や大学の中で、知らず知らずジェンダーロールが刷り込まれているのかもしれないと思いますね。よほど気を付けないとそれが再生産されてしまう。日本社会の指導的人材を育成しているような場所でも、まだまだそういうようなところがあるのだということです。だからこそ、貴学ではジェンダーロールにとらわれない女性を育成しているわけですね。
髙橋:固定的で因習的なジェンダーロールは克服すべきと常に考えているところです。
中野:経営協議会でも『女性起業家が圧倒的に少ないのは大学教育に問題がある。女子限定のアントレプレナーシップ講座を設けるべき』と指摘されています。データサイエンス領域にも少ないと。そのような外部からの声も取り入れて対策を講じていきたいと思っていますが、貴学に対する声で何か気づかれたことはありますか?
髙橋:産業界のみずほフィナンシャルグループの佐藤康博さまにも評議員にご就任いただき、データサイエンスの重要性などいろいろとご指摘をいただいています。また、「日本のインターネットの父」と呼ばれている慶應義塾大学教授の村井純先生にも、お母様が本学の卒業生ということもあって、評議員に就任してもらっています。村井先生と同じ慶應義塾大学には本学の数学科卒業生の松尾亜紀子先生が名古屋大学大学院を出た後、慶應の理工学部教授に就任されています。飛行機の爆発現象等を研究テーマにしていらっしゃいますが、戦時中の生き残りをかけてつくった数学科からそのような突出した才能の人材を輩出したわけですね。小さな学科ながらも、いかに重要かを再認識しました。
一橋大学への期待
中野:大学にはそういったダイナミズムが数十年単位で起こりますね。
髙橋:時間がかかりますね。終戦直後に設けられた教育刷新委員会の女性委員は星野あいと恵泉女学園創立者である河井道の2人だけでした。2人とも、津田梅子が1892年に創設した奨学金制度によってブリンマー大学で学んだ人材です。制度ができてから約半世紀過ぎ、ようやくその制度で留学した人が委員となり、対等にネゴシエイトして教育改革を行い、本学も新制大学への昇格を勝ち取れたわけですから。
中野:これからも、大学変革に着実に取り組んでいかなければならないと思います。そこで、最後に一橋大学への期待や注文についてお話しください。
髙橋:トップレベルの社会科学の総合大学として、貴学の大学院に本学の学生もたくさん進学しています。そういった学生たちについては、日本だけを見て完結するのではなく、アンテナを高く上げて世界の多方面に関心を向ける人材に育てていただきたいと思います。
アンテナが高いというのは、センシティブにいろいろな情報をキャッチできるということ。そこから新たなことへのチャレンジができるのです。一橋大学が建学された源流には、新たな領域での新しいことへのチャレンジがあったわけですから。一橋大学を建学した森有礼は、まだ20代半ばであるにもかかわらず、6歳で留学した津田の後見人を引き受けて津田の人格形成に寄与するという斬新な行いをしています。森有礼が日本の教育のためにアンテナを高く上げて情報収集に努め、行動した貢献は計り知れません。そんな胆力や逞しさを明治期のリーダーには感じますが、その流れを汲む一橋大学から、かような人材が輩出されることを願っています。


